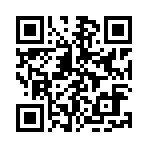2014年06月26日
今日の木地(道具のあれこれ その1)
おはようございます。やはり晴れ男なんでしょうか??
昨日は、外作業が終わった途端雨が降りました。それまでは日差しも強く暑い陽気だったんですが。
作業が順調に終えられたので助かりました。
さて今日の木地です。今日は木曜日なので関連する用語を紹介します!!
今日は道具の名称と用途などを紹介したいと思います。
木を扱う職人さんでも職種により様々ですが、僕が普段から使っている木を加工する道具を取り上げていきたいと思います。
まずは・・・
【鉋(かんな)】
材を仕上る際に使います。鉋の中にも、おおまかに削る荒仕子(あらしこ)、並々に仕上る(中仕子)、などなど同じ削る用途でも段階に応じた鉋を使います。鉋自体に決まりはないんですが、鋼の良いものほど、大切にしたいので本当の仕上げの時にしか使わない。など少しこだわりに近いものかもしれません。
その他、Lの字の隅を削る際(きわ)鉋や、シャクリ鉋、面取り鉋など加工する用途により種類はものすごく豊富にあります。
僕が日常使っているもので最低限で5~6種類と言ったところです。
最近は替え刃式と言う近代的なものもありますが、僕自身自分の研ぎ調子で仕上げたいのでほとんど使ったことがありません。
【鋸(のこぎり)】
鋸には、刃の荒い縦引き(繊維と平行に刻む)用と横引き(繊維と垂直に刻む)用があります。一般の方が、想像する表裏に刃の付いているタイプの物は、目立て職人さんが町から激減し、急激に疎遠になっています。
と言うのも、刃自体が頻繁に切れなくなるうえ、替え刃が非常に安価で流通しているのも要因の一つです。
鋸に関してはほぼ、替え刃が主流になっています。
鋸の最大の敵は鉄です。材料を挽いている際、ステープル(ホッチキスのタマ)や、釘、ビスと言ったものが状況により刺さってしまっていることがあり、これを知らずに切ってしまうと…刃はすぐさま切れなくなってしまします。
造作中など、隣で作業をしている職人が鋸を使っていて音が変わる瞬間があります。「あ。。拾ってしまったな・・・」とすぐわかります。
既に材の中に埋もれていると予測が困難でよく職人を泣かせる天敵です。
【鑿(のみ)】
いまだにこの漢字、書けません。通常の職人さんであれば、平型の叩き鑿の幅の細いものから太いものの組合せを持っています。10本組が主流でしょうか。ほりたいほず(組手を差し込む穴)の幅に合わせチョイスします。
ほり幅めいっぱいの鑿を突き初めから使うと必ず失敗します。なぜなら、木には繊維方向、目通りなどあり、木質により本来刻みたいヶ所の廻りも引っ張ってきてしまいます。その為突き初めは一回り小さい鑿で繊維を断つように刻みます。この辺の手加減は材種により異なりますが、ほぼ感触と手加減で調整していきます。一突きで硬くも緩くもなってしまうので慎重な作業になります。とにかく良く切れることが大前提です。
【毛引き(けひき)】
刻む前に印をつける道具です。この道具には先端に鋼が付いているので表面の繊維を予め切っておき仕上げを綺麗にするといった使い方が出来ます。付属の盤が定規になり、複数の隅付けもスムーズに行えます。専門的な使い勝手もあるんですがここでは簡単に紹介させてもらいます。
【玄能(げんのう)】
カナヅチのことですが、昔から玄能と呼んでいます。こちらも丸型、角型など形状の種類はありますが、僕の玄能は
打撃面が片側が平でもう片側が丸と言うタイプの物を使っています。
職種により片側がバール形状になっているものを使っている職人さんもいます。
うちの職では、おおむね60~80匁(225~300g)程度の物を皆使っていますが、個人的には100匁(375g)の物が重みもあり、使いやすく愛用しています。その為人に貸すと重いといわれます・・・
今回は刃物を中心に紹介しました。どれもただ扱うだけではなかなかうまく扱えないものですが、日頃から使い慣れた道具は、調子もよくわかり仕上も読めます。こういった部分は、木を扱う職ならではかもしれませんね。
張切って画像も用意したんですが…うまく添付できなかったのでまたの機会に。
今日は、市内を転々と施工して廻ります。順調に進むんでしょうか??
それでは今日も一日がんばりましょう!!
昨日は、外作業が終わった途端雨が降りました。それまでは日差しも強く暑い陽気だったんですが。
作業が順調に終えられたので助かりました。
さて今日の木地です。今日は木曜日なので関連する用語を紹介します!!
今日は道具の名称と用途などを紹介したいと思います。
木を扱う職人さんでも職種により様々ですが、僕が普段から使っている木を加工する道具を取り上げていきたいと思います。
まずは・・・
【鉋(かんな)】
材を仕上る際に使います。鉋の中にも、おおまかに削る荒仕子(あらしこ)、並々に仕上る(中仕子)、などなど同じ削る用途でも段階に応じた鉋を使います。鉋自体に決まりはないんですが、鋼の良いものほど、大切にしたいので本当の仕上げの時にしか使わない。など少しこだわりに近いものかもしれません。
その他、Lの字の隅を削る際(きわ)鉋や、シャクリ鉋、面取り鉋など加工する用途により種類はものすごく豊富にあります。
僕が日常使っているもので最低限で5~6種類と言ったところです。
最近は替え刃式と言う近代的なものもありますが、僕自身自分の研ぎ調子で仕上げたいのでほとんど使ったことがありません。
【鋸(のこぎり)】
鋸には、刃の荒い縦引き(繊維と平行に刻む)用と横引き(繊維と垂直に刻む)用があります。一般の方が、想像する表裏に刃の付いているタイプの物は、目立て職人さんが町から激減し、急激に疎遠になっています。
と言うのも、刃自体が頻繁に切れなくなるうえ、替え刃が非常に安価で流通しているのも要因の一つです。
鋸に関してはほぼ、替え刃が主流になっています。
鋸の最大の敵は鉄です。材料を挽いている際、ステープル(ホッチキスのタマ)や、釘、ビスと言ったものが状況により刺さってしまっていることがあり、これを知らずに切ってしまうと…刃はすぐさま切れなくなってしまします。
造作中など、隣で作業をしている職人が鋸を使っていて音が変わる瞬間があります。「あ。。拾ってしまったな・・・」とすぐわかります。
既に材の中に埋もれていると予測が困難でよく職人を泣かせる天敵です。
【鑿(のみ)】
いまだにこの漢字、書けません。通常の職人さんであれば、平型の叩き鑿の幅の細いものから太いものの組合せを持っています。10本組が主流でしょうか。ほりたいほず(組手を差し込む穴)の幅に合わせチョイスします。
ほり幅めいっぱいの鑿を突き初めから使うと必ず失敗します。なぜなら、木には繊維方向、目通りなどあり、木質により本来刻みたいヶ所の廻りも引っ張ってきてしまいます。その為突き初めは一回り小さい鑿で繊維を断つように刻みます。この辺の手加減は材種により異なりますが、ほぼ感触と手加減で調整していきます。一突きで硬くも緩くもなってしまうので慎重な作業になります。とにかく良く切れることが大前提です。
【毛引き(けひき)】
刻む前に印をつける道具です。この道具には先端に鋼が付いているので表面の繊維を予め切っておき仕上げを綺麗にするといった使い方が出来ます。付属の盤が定規になり、複数の隅付けもスムーズに行えます。専門的な使い勝手もあるんですがここでは簡単に紹介させてもらいます。
【玄能(げんのう)】
カナヅチのことですが、昔から玄能と呼んでいます。こちらも丸型、角型など形状の種類はありますが、僕の玄能は
打撃面が片側が平でもう片側が丸と言うタイプの物を使っています。
職種により片側がバール形状になっているものを使っている職人さんもいます。
うちの職では、おおむね60~80匁(225~300g)程度の物を皆使っていますが、個人的には100匁(375g)の物が重みもあり、使いやすく愛用しています。その為人に貸すと重いといわれます・・・
今回は刃物を中心に紹介しました。どれもただ扱うだけではなかなかうまく扱えないものですが、日頃から使い慣れた道具は、調子もよくわかり仕上も読めます。こういった部分は、木を扱う職ならではかもしれませんね。
張切って画像も用意したんですが…うまく添付できなかったのでまたの機会に。
今日は、市内を転々と施工して廻ります。順調に進むんでしょうか??
それでは今日も一日がんばりましょう!!
Posted by 大橋木工所 at 07:00│Comments(0)
│今日の木地録