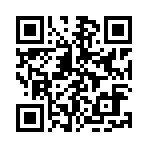2014年11月28日
今日の木地(北米材~その9~)
おはようございます。今週もあっという間に週末ですね。
さて、取り上げてきた北米材も一旦今日で最後です。
今日はレッドオークとベイモミを取り上げていきたいと思います。
レッドオーク

引用(一財)日本木材総合情報センター
全米に分布している材ですが主には中東部から産出されているようです。ホワイトオークと同じブナ科ですが属が違う材です。属が違うとどうなのかは詳しく分かりませんが、近いようですが材としては区別されているということでしょうか。
ホワイトオークが、ウィスキーの熟成に適しているのに対し、この材は適さないとされています。
ホワイトオークに比べると耐久性は低いですが、材自体は重く硬く衝撃に強い材です。日本にはホワイトオークの方が多く輸入されているよです。
収縮が大きく割れ曲など狂いが出る為、あまり高く評価されていません。
ベイモミ

引用(一財)日本木材総合情報センター
東部で産出されるものをイーストファー、西部で産出されるものをウェスタンファーと呼ばれ日本で流通しているもののほとんどはウェスタンファーの様です。
複数の種がありますが流通する場合は、区別せずにベイモミとしてまとめられています。場合によりベイツガと一括されている場合もあるようです。
国産のモミに比べると、長く大きな材が採りやすい種ですが、特徴的には国内のものとほぼ同じようです。
耐久性が低く地面に接地した用途には向かないです。木材としては様々な用途に用いられている材の様です。
今日は午前中にお約束が立込んでいます。順調に納まるでしょうか。
今日も一日がんばりましょう‼
さて、取り上げてきた北米材も一旦今日で最後です。
今日はレッドオークとベイモミを取り上げていきたいと思います。
レッドオーク

引用(一財)日本木材総合情報センター
全米に分布している材ですが主には中東部から産出されているようです。ホワイトオークと同じブナ科ですが属が違う材です。属が違うとどうなのかは詳しく分かりませんが、近いようですが材としては区別されているということでしょうか。
ホワイトオークが、ウィスキーの熟成に適しているのに対し、この材は適さないとされています。
ホワイトオークに比べると耐久性は低いですが、材自体は重く硬く衝撃に強い材です。日本にはホワイトオークの方が多く輸入されているよです。
収縮が大きく割れ曲など狂いが出る為、あまり高く評価されていません。
ベイモミ

引用(一財)日本木材総合情報センター
東部で産出されるものをイーストファー、西部で産出されるものをウェスタンファーと呼ばれ日本で流通しているもののほとんどはウェスタンファーの様です。
複数の種がありますが流通する場合は、区別せずにベイモミとしてまとめられています。場合によりベイツガと一括されている場合もあるようです。
国産のモミに比べると、長く大きな材が採りやすい種ですが、特徴的には国内のものとほぼ同じようです。
耐久性が低く地面に接地した用途には向かないです。木材としては様々な用途に用いられている材の様です。
今日は午前中にお約束が立込んでいます。順調に納まるでしょうか。
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月27日
今日の木地(北米材~その8~)
おはようございます。昨日は降ったりやんだりとあまり良いお天気ではなかったですね。
さて今日の木地録では、北米材の続きを。
今日はバスウッドとブラックチェリーを取り上げたいと思います。
バスウッド

引用(一財)日本木材総合情報センター
シナノキと同類で木目がおとなしく塗装下地として非常に定評があるシナノキと同じような用途に用いられています。
主には米国北東部五大湖のあたりで産出されているよです。
成長も早く大きくなる材で、軽軟で加工性は高い材ですが、保存性が低く虫害を受けやすいようです。
バスウッドのほかリンデン、アメリカンホワイトウッドなどと呼ばれていることもあります。
既述の通り、塗装下地や家具材、内装材などに用いられますが、楽器などにも用いられているようです。
ブラックチェリー

引用(一財)日本木材総合情報センター
バラ科の材で米国東部の広い範囲で生育しているようです。ワイルドチェリーと呼ばれていることもあります。
心材は淡い紅褐色~濃い紅褐色で、使い込むほど飴色に変色する特性があります。
材面にガムポケットと呼ばれる樹脂の痕跡が黒く表れることがあります。
北米の数あるサクラ類の中でも木材として利用される物はこの種のものがほとんどの様です。
家具やキャビネットなどに用いられますが、燻製のチップなどもこの材が適していると用いられているようです。
さて・・・そろそろ次なるイベントの準備にかからなくては!と思いつつ日にちだけが過ぎています。
今日も一日がんばりましょう‼
さて今日の木地録では、北米材の続きを。
今日はバスウッドとブラックチェリーを取り上げたいと思います。
バスウッド

引用(一財)日本木材総合情報センター
シナノキと同類で木目がおとなしく塗装下地として非常に定評があるシナノキと同じような用途に用いられています。
主には米国北東部五大湖のあたりで産出されているよです。
成長も早く大きくなる材で、軽軟で加工性は高い材ですが、保存性が低く虫害を受けやすいようです。
バスウッドのほかリンデン、アメリカンホワイトウッドなどと呼ばれていることもあります。
既述の通り、塗装下地や家具材、内装材などに用いられますが、楽器などにも用いられているようです。
ブラックチェリー

引用(一財)日本木材総合情報センター
バラ科の材で米国東部の広い範囲で生育しているようです。ワイルドチェリーと呼ばれていることもあります。
心材は淡い紅褐色~濃い紅褐色で、使い込むほど飴色に変色する特性があります。
材面にガムポケットと呼ばれる樹脂の痕跡が黒く表れることがあります。
北米の数あるサクラ類の中でも木材として利用される物はこの種のものがほとんどの様です。
家具やキャビネットなどに用いられますが、燻製のチップなどもこの材が適していると用いられているようです。
さて・・・そろそろ次なるイベントの準備にかからなくては!と思いつつ日にちだけが過ぎています。
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月26日
今日の木地(北米材~その7~)
おはようございます。昨日は雨で予定の現場作業がすべて延期になってしまいました。
今日はどんな一日になるんでしょうか??
今日も引き続き、北米材を取り上げていきたいと思います。
今日はベイヒとベイヒバ。米国産のヒノキとヒバですね。
まずはベイヒ

引用(一財)日本木材総合情報センター
オレゴン州、カリフォルニア州などから産出される材で、国産ヒノキの代用で用いられる場合があります。
日本ではヒノキというと非常に評価が高く人気もあるため、価格も高い傾向ですがアメリカではそれほど評価されておらず、徐々に輸入されるようになってきたようです。記録上では明治後半から輸入されていたようです。
静岡は比較的ヒノキが手に入りやすいので、ほとんど国産ヒノキでまとまりますが、そうでない場合は、予算などに応じてベイヒを用いたりしているようです。
性質的にもかなり似ており、なかなか見分けがつきにくいです。国産の物に比べ香りがきついのが特徴の様です。
ベイヒバ

引用(一財)日本木材総合情報センター
こちらの材もヒノキ科です。オレゴン~アラスカにかけて産出されています。
こちらの材も国産のヒバに良く似ており、耐久性は高く加工性が高いのが特徴の様です。ボートや細工、家具などに用いられてる他、土台などの用途にも使われているようです。
ただ既述の通り、静岡はヒノキが容易に手に入るので、こちらの材もあまり流通していない印象が強いです。
こちらの材も独特の芳香が強烈で、すぐさま判別出来るほど匂うようです。
どちらも国産に見た目は似ているものの、芳香が強烈というのが判別の基準の一つかもしれません。
さて、月末が迫っており、たくさん忘年会のお誘いをもらっていますが・・・全部出ちゃおうかな!?なんて考えてます(笑)
今日も一日がんばりましょう‼
今日はどんな一日になるんでしょうか??
今日も引き続き、北米材を取り上げていきたいと思います。
今日はベイヒとベイヒバ。米国産のヒノキとヒバですね。
まずはベイヒ

引用(一財)日本木材総合情報センター
オレゴン州、カリフォルニア州などから産出される材で、国産ヒノキの代用で用いられる場合があります。
日本ではヒノキというと非常に評価が高く人気もあるため、価格も高い傾向ですがアメリカではそれほど評価されておらず、徐々に輸入されるようになってきたようです。記録上では明治後半から輸入されていたようです。
静岡は比較的ヒノキが手に入りやすいので、ほとんど国産ヒノキでまとまりますが、そうでない場合は、予算などに応じてベイヒを用いたりしているようです。
性質的にもかなり似ており、なかなか見分けがつきにくいです。国産の物に比べ香りがきついのが特徴の様です。
ベイヒバ

引用(一財)日本木材総合情報センター
こちらの材もヒノキ科です。オレゴン~アラスカにかけて産出されています。
こちらの材も国産のヒバに良く似ており、耐久性は高く加工性が高いのが特徴の様です。ボートや細工、家具などに用いられてる他、土台などの用途にも使われているようです。
ただ既述の通り、静岡はヒノキが容易に手に入るので、こちらの材もあまり流通していない印象が強いです。
こちらの材も独特の芳香が強烈で、すぐさま判別出来るほど匂うようです。
どちらも国産に見た目は似ているものの、芳香が強烈というのが判別の基準の一つかもしれません。
さて、月末が迫っており、たくさん忘年会のお誘いをもらっていますが・・・全部出ちゃおうかな!?なんて考えてます(笑)
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月25日
今日の木地(北米材~その6~)
おはようございます。今週も始まりました♪
さて今日の木地録も北米材を紹介していきたいと思います。
今日は、ベイツガ、ベイスギを取り上げたいと思います。
ベイツガ

引用(一財)日本木材総合情報センター
主にはアラスカ南部で産出される材で、アメリカから輸入する材で最も輸入量の多い材の様です。
国内のツガに比べ、評価はあまり高くなく金額的に安価な為手軽に使える印象です。
建築用途に用いられることが多くその他、箱材やパルプと言った用途に用いられています。
あまり耐久性の高くなく水分がある所では腐るなど、特性上用途には注意が必要な材かもしれません。
続いてベイスギ

引用(一財)日本木材総合情報センター
国産の材に比べ赤身が強い印象です。主にはアラスカ南東~カルフォルニア北西などいった地域に生育しており、
国内のスギと同種でありながら別物です。
加工性は良く、保存性は非常に高いようですが軽軟で強い材とは言えない材のようです。
先住民インディアンがこの種の材を使っててトーテムポールなどを造っていたことが有名で、既述の加工しやすく保存性が高いという特性が表れているように思います。
ウェスタンレッドシーダーなどと呼ばれることもあります。
北米材にはベイ○○と呼ばれる材がいくつかあります。比較的以前より国内でも馴染みがあったということだと思います。
さて今週は火曜スタートですが張切っていきましょう!
今日も一日がんばりましょう‼
さて今日の木地録も北米材を紹介していきたいと思います。
今日は、ベイツガ、ベイスギを取り上げたいと思います。
ベイツガ

引用(一財)日本木材総合情報センター
主にはアラスカ南部で産出される材で、アメリカから輸入する材で最も輸入量の多い材の様です。
国内のツガに比べ、評価はあまり高くなく金額的に安価な為手軽に使える印象です。
建築用途に用いられることが多くその他、箱材やパルプと言った用途に用いられています。
あまり耐久性の高くなく水分がある所では腐るなど、特性上用途には注意が必要な材かもしれません。
続いてベイスギ

引用(一財)日本木材総合情報センター
国産の材に比べ赤身が強い印象です。主にはアラスカ南東~カルフォルニア北西などいった地域に生育しており、
国内のスギと同種でありながら別物です。
加工性は良く、保存性は非常に高いようですが軽軟で強い材とは言えない材のようです。
先住民インディアンがこの種の材を使っててトーテムポールなどを造っていたことが有名で、既述の加工しやすく保存性が高いという特性が表れているように思います。
ウェスタンレッドシーダーなどと呼ばれることもあります。
北米材にはベイ○○と呼ばれる材がいくつかあります。比較的以前より国内でも馴染みがあったということだと思います。
さて今週は火曜スタートですが張切っていきましょう!
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月21日
今日の木地(北米材~その5~)
おはようございます。昨日はお天気の影響で予定が大幅に変更し非常に慌ただしい一日になりました。
今日はどんな一日になるんでしょうか??
木地録では引き続き北米材を取り上げたいと思います。
今日は、スプルスと米松。
まずはスプルス

引用(一財)日本木材総合情報センター
主にはアラスカ・カナダなどで産出されていますが、ロシアや北海道などにも分布しています。
良材として扱われ色々な用途に用いられています。材自体白く焼けやすい印象です。
マツ科に属している材ですが、さほど脂分が多くない特徴です。いくつか同種の物もスプルスとして流通しているものもあります。
国内ではベイトウヒとも呼ばれている場合もありますが、スプルスと呼ぶことが一般的です。
続いてベイマツ
引用(一財)日本木材総合情報センター
国内ではなぜかこの材はベイマツと呼ばれていますが、ほかは似た種のものはパインと呼ばれています。
ピーラなどと呼ばれていることもあります。主には北米の西部に分布しており沿岸域に生育しているものと山岳域に生育しているものとで特性が異なります。
マツと呼ばれていますが、国内のマツとは同属ではありません。
木材の名称、通称は本当に面白く同属でも呼び方が違ったり全く違う材を同じような名称で呼ぶのが、いつも不思議に思うんですが、あだ名に近い名称の印象です。非常にあいまいな部分が多いです。
さて!今週も残りわずかです。
今日も一日がんばりましょう‼
今日はどんな一日になるんでしょうか??
木地録では引き続き北米材を取り上げたいと思います。
今日は、スプルスと米松。
まずはスプルス

引用(一財)日本木材総合情報センター
主にはアラスカ・カナダなどで産出されていますが、ロシアや北海道などにも分布しています。
良材として扱われ色々な用途に用いられています。材自体白く焼けやすい印象です。
マツ科に属している材ですが、さほど脂分が多くない特徴です。いくつか同種の物もスプルスとして流通しているものもあります。
国内ではベイトウヒとも呼ばれている場合もありますが、スプルスと呼ぶことが一般的です。
続いてベイマツ

引用(一財)日本木材総合情報センター
国内ではなぜかこの材はベイマツと呼ばれていますが、ほかは似た種のものはパインと呼ばれています。
ピーラなどと呼ばれていることもあります。主には北米の西部に分布しており沿岸域に生育しているものと山岳域に生育しているものとで特性が異なります。
マツと呼ばれていますが、国内のマツとは同属ではありません。
木材の名称、通称は本当に面白く同属でも呼び方が違ったり全く違う材を同じような名称で呼ぶのが、いつも不思議に思うんですが、あだ名に近い名称の印象です。非常にあいまいな部分が多いです。
さて!今週も残りわずかです。
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月20日
今日の木地(北米材~その4~)
おはようございます。週も後半戦に突入ですね。
さて、今日の木地録では引き続き北米材を取り上げていきたいと思います。
今日はホワイトオークとメープル。
まずはホワイトオーク。

引用(一財)日本木材総合情報センター
昔からウィスキーなどを熟成させる樽に用いられている材で、主には、大陸の北川、フロリダ~カナダで産出される材です。
国内のミズナラに非常によく似ており同じような用途に用いられています。
この名称で呼ばれている材にはいくつか種類があるようですが、ひとまとめにホワイトオーク呼ばれて流通しています。
高級材として知られていますが、重硬な材の為、収縮率が高く乾燥時の割れやひびが起こりやすいので注意が必要です。
昔から安定した人気のある材です。
続いてメープル

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録ではいくつかメイプルを取り上げていますが、カエデ科の材です。カナダ・アメリカ北東部で産出される材で
す。鳥眼杢と呼ばれる玉粒状の杢のあらわれている材をバーズアイメイプルなどと呼ぶこともあります。
こういった珍しい杢が現れた材は、価値が評価され高値で流通します。
材料によりシュガ―メイプル、ブラックメイプルなどと呼ばれていることもあります。
野球のバットやボウリングのピンにも用いられる材で衝撃に強いのが特徴です。
今日は個人的に好きな材を2つ取り上げましたがどちらも人気のある材なので、比較的触れる機会も多いのではないかなと思います。
今日も一日がんばりましょう‼
さて、今日の木地録では引き続き北米材を取り上げていきたいと思います。
今日はホワイトオークとメープル。
まずはホワイトオーク。

引用(一財)日本木材総合情報センター
昔からウィスキーなどを熟成させる樽に用いられている材で、主には、大陸の北川、フロリダ~カナダで産出される材です。
国内のミズナラに非常によく似ており同じような用途に用いられています。
この名称で呼ばれている材にはいくつか種類があるようですが、ひとまとめにホワイトオーク呼ばれて流通しています。
高級材として知られていますが、重硬な材の為、収縮率が高く乾燥時の割れやひびが起こりやすいので注意が必要です。
昔から安定した人気のある材です。
続いてメープル

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録ではいくつかメイプルを取り上げていますが、カエデ科の材です。カナダ・アメリカ北東部で産出される材で
す。鳥眼杢と呼ばれる玉粒状の杢のあらわれている材をバーズアイメイプルなどと呼ぶこともあります。
こういった珍しい杢が現れた材は、価値が評価され高値で流通します。
材料によりシュガ―メイプル、ブラックメイプルなどと呼ばれていることもあります。
野球のバットやボウリングのピンにも用いられる材で衝撃に強いのが特徴です。
今日は個人的に好きな材を2つ取り上げましたがどちらも人気のある材なので、比較的触れる機会も多いのではないかなと思います。
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月19日
今日の木地(北米材~その3~)
おはようございます。段々と朝晩冷え込むようになってきましたね。
さて今日の木地録では、北米材を引き続き取り上げていきたいと思います。
今日はバーチとアッシュ。日本でも比較的触れる機会の多い材だと思います。
バーチ

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録では、イエローバーチとして紹介しました。主にはカナダ、アメリカ北東部で産出される材でカバノキ科に属します。
国内のミズメやマカンバなどとほぼ同じで、比較的穏やかな木目です。
家具や内装材に使われるだけあって加工性は良く、仕上がりは非常にきれいに仕上がります。
ここ近年、バーチという名称を聞くようになってきている印象です。
アッシュ

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録では、ホワイトアッシュとして取り上げています。アッシュ自体は北米全域で生育している材ですが、主には中東部に多いようです。
アオダモと同種で同じ用途に用いられています。モクセイ科の材でトリネコなどと呼ばれていることもあります。
耐久性があり曲げにも適していることもあり、昔はテニスラケットなどに用いられていました。
内装材としても色々な用途に使われています。個人的に好きな塩地という材とも同等として扱われているようです。
木材を調べている中で、以前は木材で造られていたものが、他の原料に変わり今では木材で生産されなくなっているものが多くあり、時代の流れ・技術の進歩とはいえ少し残念な気もします。
木の特性を活かせる用途での使い道がたくさんあると嬉しいですね。
今日も一日がんばりましょう‼
さて今日の木地録では、北米材を引き続き取り上げていきたいと思います。
今日はバーチとアッシュ。日本でも比較的触れる機会の多い材だと思います。
バーチ

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録では、イエローバーチとして紹介しました。主にはカナダ、アメリカ北東部で産出される材でカバノキ科に属します。
国内のミズメやマカンバなどとほぼ同じで、比較的穏やかな木目です。
家具や内装材に使われるだけあって加工性は良く、仕上がりは非常にきれいに仕上がります。
ここ近年、バーチという名称を聞くようになってきている印象です。
アッシュ

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録では、ホワイトアッシュとして取り上げています。アッシュ自体は北米全域で生育している材ですが、主には中東部に多いようです。
アオダモと同種で同じ用途に用いられています。モクセイ科の材でトリネコなどと呼ばれていることもあります。
耐久性があり曲げにも適していることもあり、昔はテニスラケットなどに用いられていました。
内装材としても色々な用途に使われています。個人的に好きな塩地という材とも同等として扱われているようです。
木材を調べている中で、以前は木材で造られていたものが、他の原料に変わり今では木材で生産されなくなっているものが多くあり、時代の流れ・技術の進歩とはいえ少し残念な気もします。
木の特性を活かせる用途での使い道がたくさんあると嬉しいですね。
今日も一日がんばりましょう‼
Posted by 大橋木工所 at
07:00
│Comments(0)
2014年11月18日
今日の木地(北米材~その2~)
おはようございます。昨日は、現場の方も順調に終わりホッと一安心です。
今日はまたまた慌ただしい一日なりそうです。
さて、今日の木地録は、引き続き北米材を取り上げていきたいと思います。
今日は、ヒッコリーとレッドウッドという材です。
まずヒッコリー

引用(一財)日本木材総合情報センター
クルミ科の材で、主にはアメリカ東部で産出されます。硬い材で加工性があまり良くありません。釘やビスの保持性は高い材ですが、割れやすいので下穴など事前の加工が必要なようです。
ヒッコリーストライプと呼ばれるストライプは、元々この材の繊細な木目に似ている模様ということで命名されているようです。
その木地を使ったデニムは伐採職人が愛用していたようで、なんだかつながりを感じます。
続いて、レッドウッド。

引用(一財)日本木材総合情報センター
セコイアとも呼ばれる材で、スギ科の材で針葉樹です。こちらはアメリカ西岸で産出される材で農作物が良く育つ豊かな土地で生育する種の様です。
耐久性が高く、比較的屋外にも用いられる材で、ベンチやウッドデッキなど幅広く使われています。
軽軟で加工性が良く耐久性・保存性が高いというのが、スギに似ているのかもしれません。
資料では樹高100Mにも達する世界最長のものが生育してるようです。
月末月初で慌ただしくなりそうな見込みです。もうすぐ年末ですね・・・
今日も一日がんばりましょう‼
今日はまたまた慌ただしい一日なりそうです。
さて、今日の木地録は、引き続き北米材を取り上げていきたいと思います。
今日は、ヒッコリーとレッドウッドという材です。
まずヒッコリー

引用(一財)日本木材総合情報センター
クルミ科の材で、主にはアメリカ東部で産出されます。硬い材で加工性があまり良くありません。釘やビスの保持性は高い材ですが、割れやすいので下穴など事前の加工が必要なようです。
ヒッコリーストライプと呼ばれるストライプは、元々この材の繊細な木目に似ている模様ということで命名されているようです。
その木地を使ったデニムは伐採職人が愛用していたようで、なんだかつながりを感じます。
続いて、レッドウッド。

引用(一財)日本木材総合情報センター
セコイアとも呼ばれる材で、スギ科の材で針葉樹です。こちらはアメリカ西岸で産出される材で農作物が良く育つ豊かな土地で生育する種の様です。
耐久性が高く、比較的屋外にも用いられる材で、ベンチやウッドデッキなど幅広く使われています。
軽軟で加工性が良く耐久性・保存性が高いというのが、スギに似ているのかもしれません。
資料では樹高100Mにも達する世界最長のものが生育してるようです。
月末月初で慌ただしくなりそうな見込みです。もうすぐ年末ですね・・・
今日も一日がんばりましょう‼
Posted by 大橋木工所 at
07:00
│Comments(0)
2014年11月17日
今日の木地(北米材~その1~)
おはようございます。今週も張切っていきましょう‼
さて今日から北米材を取り上げていきたと思います。
まずは・・・ウォルナットとビーチ。
ウォルナット

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録では、ブラックウォルナットとして紹介しましたが、クルミ科の材で主にはアメリカ、カナダ東部で産出されるものです。
この材は国内での人気も非常に高く、世界的にも高級材として扱われています。
ただ、輸出量の増加でアメリカでは輸出は制限されているようで、代用材が用いられている現状です。
耐久性、加工性、仕上がりの評価も総合的に高くとても良材です。
ウォルナット自体は、塗装をしない状態でもツヤのある独特の質感できれいな表面です。これも世界的に高級材として扱われている要因の一つかもしれません。
続いてビーチ

引用(一財)日本木材総合情報センター
ブナ材と区別がつかなほど似ており、ブナの代用材として知られている材です。
主にアメリカ東部で産出されています。北欧でも産出されますが、北米産の物は色が濃くムラがあるのが特徴の様です。
粘りのある材で曲げに強いことで知られているので、そういった用途の加工などに用いられています。
ブナ科で木目が特徴的な材です。材が無味無臭の為、食器棚などに用いられることがあります。
さて月曜日です。今週はどんな週になるんでしょうか?
今日も一日がんばりましょう‼
さて今日から北米材を取り上げていきたと思います。
まずは・・・ウォルナットとビーチ。
ウォルナット

引用(一財)日本木材総合情報センター
木地録では、ブラックウォルナットとして紹介しましたが、クルミ科の材で主にはアメリカ、カナダ東部で産出されるものです。
この材は国内での人気も非常に高く、世界的にも高級材として扱われています。
ただ、輸出量の増加でアメリカでは輸出は制限されているようで、代用材が用いられている現状です。
耐久性、加工性、仕上がりの評価も総合的に高くとても良材です。
ウォルナット自体は、塗装をしない状態でもツヤのある独特の質感できれいな表面です。これも世界的に高級材として扱われている要因の一つかもしれません。
続いてビーチ

引用(一財)日本木材総合情報センター
ブナ材と区別がつかなほど似ており、ブナの代用材として知られている材です。
主にアメリカ東部で産出されています。北欧でも産出されますが、北米産の物は色が濃くムラがあるのが特徴の様です。
粘りのある材で曲げに強いことで知られているので、そういった用途の加工などに用いられています。
ブナ科で木目が特徴的な材です。材が無味無臭の為、食器棚などに用いられることがあります。
さて月曜日です。今週はどんな週になるんでしょうか?
今日も一日がんばりましょう‼
2014年11月14日
今日の木地(アジア材~ラスト~)
おはようございます。あっという間に週末ですね。
アジア材はまだまだありますが、今週で最後にしたいと思います。
最後はラミンとローズウッドを取り上げたいと思います。
ラミン

引用(一財)日本木材総合情報センター
主にはフィリピンなどから産出される材ですが、他地域でも成育しています。
若干重硬ではありますが、加工性も悪くなく仕上がりも良好です。ただ乾燥時などに割れが起こりやすく
釘などの打ち込みも注意が必要な材です。
変色菌の影響を受けやすく、また乾燥時に悪臭を放つことで知られているようです。
白く穏やかな材で内装材などに用いられています。
ローズウッド

引用(一財)日本木材総合情報センター
似たような別物の材が○○ローズウッドと呼ばれ出回っている材です。
本もの(正規の物)はマメ科で重硬で高耐久で材としての評価は高いですが、加工性があまり良くない印象です。
比較的細かな細工物に物に用いられているようです。
シタンと呼ばれ人気がある材ですが、高価な材の為代用材が出回っているのではないかと思います。
種によってはレッドリストに記載されている為、輸出などに制限がかかっているものもあるようです。
主にはインドやインドネシアなどで産出される材ですが、現在では非常に入手が困難な材になっています。
さて、今週も非常に慌ただしい毎日でした。まだまだ土曜まで予定がぎっしりです。
今日も一日がんばりましょう‼
アジア材はまだまだありますが、今週で最後にしたいと思います。
最後はラミンとローズウッドを取り上げたいと思います。
ラミン

引用(一財)日本木材総合情報センター
主にはフィリピンなどから産出される材ですが、他地域でも成育しています。
若干重硬ではありますが、加工性も悪くなく仕上がりも良好です。ただ乾燥時などに割れが起こりやすく
釘などの打ち込みも注意が必要な材です。
変色菌の影響を受けやすく、また乾燥時に悪臭を放つことで知られているようです。
白く穏やかな材で内装材などに用いられています。
ローズウッド

引用(一財)日本木材総合情報センター
似たような別物の材が○○ローズウッドと呼ばれ出回っている材です。
本もの(正規の物)はマメ科で重硬で高耐久で材としての評価は高いですが、加工性があまり良くない印象です。
比較的細かな細工物に物に用いられているようです。
シタンと呼ばれ人気がある材ですが、高価な材の為代用材が出回っているのではないかと思います。
種によってはレッドリストに記載されている為、輸出などに制限がかかっているものもあるようです。
主にはインドやインドネシアなどで産出される材ですが、現在では非常に入手が困難な材になっています。
さて、今週も非常に慌ただしい毎日でした。まだまだ土曜まで予定がぎっしりです。
今日も一日がんばりましょう‼