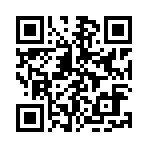2014年08月30日
今日の木地(マトア)
おはようございます。八月最後の営業日になりました。週明けは9月ですね。本当に早くてびっくりです。
さて今日の木地では、マトアという材を取り上げたいと思います。

名称:マトア、タウン(ムクロジ科)
広葉樹
地域:熱帯アジア、他(スリランカ~ニューギニアなど)
引用(一財)日本木材総合情報センター
この材を主に輸出している国は複数ありますが、インドネシアではマトア、ニューギニアではタウンという名称で呼ばれています。
メランチ類程大量に得られませんが日本に輸入されている材の中でも、常に上位に入っている材の様です。
以前は複数の種を総称して呼ばれていることもあったようですが、ここ最近は一種呼ぶようになって、材料の差は産地や環境による差の様です。
材としては木理は交錯し、重硬な材で保存性も高いです。切削、加工性は良く建築の装飾や家具などの用途に用いられています。
ただ原木の丸太形状があまり良いとは言えず材としてはあまり取りの良いものではなさそうです。
どこかで見たことがあるような材ですが、扱った記憶がなく分かりませんが、見る限りでは扱いに困る材ではなさそうです。
さてさて、木地録開始から平日6日間毎日更新してきましたが、9月から月~金の更新にしていきたいと思います。
というわけで、土曜の更新は今日で最後です。
では、今日も一日がんばりましょう‼
さて今日の木地では、マトアという材を取り上げたいと思います。

名称:マトア、タウン(ムクロジ科)
広葉樹
地域:熱帯アジア、他(スリランカ~ニューギニアなど)
引用(一財)日本木材総合情報センター
この材を主に輸出している国は複数ありますが、インドネシアではマトア、ニューギニアではタウンという名称で呼ばれています。
メランチ類程大量に得られませんが日本に輸入されている材の中でも、常に上位に入っている材の様です。
以前は複数の種を総称して呼ばれていることもあったようですが、ここ最近は一種呼ぶようになって、材料の差は産地や環境による差の様です。
材としては木理は交錯し、重硬な材で保存性も高いです。切削、加工性は良く建築の装飾や家具などの用途に用いられています。
ただ原木の丸太形状があまり良いとは言えず材としてはあまり取りの良いものではなさそうです。
どこかで見たことがあるような材ですが、扱った記憶がなく分かりませんが、見る限りでは扱いに困る材ではなさそうです。
さてさて、木地録開始から平日6日間毎日更新してきましたが、9月から月~金の更新にしていきたいと思います。
というわけで、土曜の更新は今日で最後です。
では、今日も一日がんばりましょう‼
2014年08月29日
今日の木地(ダークレッドメランチ)
おはようございます。昨日はあちこち本当にバタバタな一日でした。今日はどんな一日になるんでしょうか??
さて今日の木地では、ダークレッドメランチ類を取り上げたいと思います。

名称:ダークレッドメランチ(フタバガキ科)
広葉樹
地域:タイ、マラヤ、フィリピンなど
一応、材名としてあげましたが、正確にはフタバガキ科の濃い赤褐色をした材を総称してダークレッドメランチと
呼んでいるようです。
正直、僕自身も"メランチ"と聞いてもあまりピンとこない部分はありましたが、以前で言うラワン材の代用材を産地周辺国から、採取するようになり産地により呼び名が様々な為、こういった呼び方に落ち着いたみたいです。
材としては心材は、比較的濃い赤褐色で辺材との境ははっきりしています。
材には、メランチ類特有の樹脂道があり独特の木肌です。木理は交錯していますが加工性は良く、光沢があるきれいな仕上がりになります。
メランチ類の中でも保存性は高いものの、虫害を受けやすく他の材に比べると注意が必要です。
用途としては合板、建築、建具、家具などかなり幅広く用いられていましたが、ラワン材を用いることは現在は非常に少なくなっています。
以前、相当量の消費により材自体の供給(成育)が落ち込み次第に流量も減りました。
建具・枠材といえば‼といった時期もありましたが、最近ではラワンは希少材になり扱うこともほとんどなくなっていしまいました。
さて、週末ですね。
今日も一日がんばりましょう‼
さて今日の木地では、ダークレッドメランチ類を取り上げたいと思います。

名称:ダークレッドメランチ(フタバガキ科)
広葉樹
地域:タイ、マラヤ、フィリピンなど
一応、材名としてあげましたが、正確にはフタバガキ科の濃い赤褐色をした材を総称してダークレッドメランチと
呼んでいるようです。
正直、僕自身も"メランチ"と聞いてもあまりピンとこない部分はありましたが、以前で言うラワン材の代用材を産地周辺国から、採取するようになり産地により呼び名が様々な為、こういった呼び方に落ち着いたみたいです。
材としては心材は、比較的濃い赤褐色で辺材との境ははっきりしています。
材には、メランチ類特有の樹脂道があり独特の木肌です。木理は交錯していますが加工性は良く、光沢があるきれいな仕上がりになります。
メランチ類の中でも保存性は高いものの、虫害を受けやすく他の材に比べると注意が必要です。
用途としては合板、建築、建具、家具などかなり幅広く用いられていましたが、ラワン材を用いることは現在は非常に少なくなっています。
以前、相当量の消費により材自体の供給(成育)が落ち込み次第に流量も減りました。
建具・枠材といえば‼といった時期もありましたが、最近ではラワンは希少材になり扱うこともほとんどなくなっていしまいました。
さて、週末ですね。
今日も一日がんばりましょう‼
2014年08月28日
今日の木地(レッドメイプル、シルバーメイプル)
おはようございます。昨日はすごしやすい一日で作業もしやすいお天気でした。そろそろ八月も終わりますね。
さて今日の木地では、レッドメイプル、シルバーメイプルを取り上げたいと思います。

名称:レッドメイプル、シルバーメイプル(カエデ科)
広葉樹
地域:カナダ、アメリカ
引用(一財)日本木材総合情報センター
どちらも性質が非常によく似た材で、輸入される際は混合されソフトメイプル類といったようにまとめられていることが多いようです。なので今日の木地でも、併せて取り上げることにしました。
材としては、比較的重硬ではあるものの、ハードメイプルに比べると軽軟な材なので、ハードメイプルが用いられる用途で、硬さなどを必要としない用途の場合に、このソフトメイプル類が用いられることが多いようです。
主には、家具、ドア、合板などに用いられ、その他、梱包材やパレットなどにも用いられています。
レッドメイプルは淡褐色で、シルバーメイプルは白い材がほとんどです。この材も産地より色が様々です。
メイプル類は、加工性が良い印象あり個人的にも好きです。
レッドメイプル、シルバーメイプルと区別して扱ったことがないな。と思っていたらひとくくりで扱われていると知り納得です。
うちでは、ソフトメイプル系よりもハードメイプルを扱ったことがほとんどだと思います。
さて今日は、今日は午前午後とも別件で動く為、作業がスムーズに進むと助かるんですが。どうでしょうか。
今日も一日がんばりましょう!!
さて今日の木地では、レッドメイプル、シルバーメイプルを取り上げたいと思います。

名称:レッドメイプル、シルバーメイプル(カエデ科)
広葉樹
地域:カナダ、アメリカ
引用(一財)日本木材総合情報センター
どちらも性質が非常によく似た材で、輸入される際は混合されソフトメイプル類といったようにまとめられていることが多いようです。なので今日の木地でも、併せて取り上げることにしました。
材としては、比較的重硬ではあるものの、ハードメイプルに比べると軽軟な材なので、ハードメイプルが用いられる用途で、硬さなどを必要としない用途の場合に、このソフトメイプル類が用いられることが多いようです。
主には、家具、ドア、合板などに用いられ、その他、梱包材やパレットなどにも用いられています。
レッドメイプルは淡褐色で、シルバーメイプルは白い材がほとんどです。この材も産地より色が様々です。
メイプル類は、加工性が良い印象あり個人的にも好きです。
レッドメイプル、シルバーメイプルと区別して扱ったことがないな。と思っていたらひとくくりで扱われていると知り納得です。
うちでは、ソフトメイプル系よりもハードメイプルを扱ったことがほとんどだと思います。
さて今日は、今日は午前午後とも別件で動く為、作業がスムーズに進むと助かるんですが。どうでしょうか。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年08月27日
今日の木地(セプター)
おはようございます。
今日の木地ではセプターという材を取り上げたいと思います。

名称:セプター(マメ科)
広葉樹
地域:タイ、カンボジア、スマトラなど
引用(一財)日本木材総合情報センター
shindoraと分類される材とpseudosindoraと分類される種を総称し、セプターとして扱われています。
東南アジアを中心に生息し約20種ほどある種です。分布も広い為、産出国により名称も異なります。
樹種により芯材の色が異なる材で濃い赤褐色から、淡色桃色と色は様々です。
材としては木理は通直もしくは、若干交錯しており、加工性は少し良くないようで保存性は樹種により異なり材料の色が濃いほど重硬で保存性も高く、色が薄いほど軽軟で低いとされています。
フタバガキ科のラワンなどと木目に現れる樹脂道と呼ばれる細胞間道が同じように並んでいるのがshindoraに分類される種の特徴で他の材と見分けが容易です。
用途としては、家具などを中心にキャビネットなどに用いられ濃い色の縞が表面にあるものは装飾材として用いられているようです。
分布が複数国にまたがる材は、名称も様々でおもしろいです。
ほとんど扱うことのない材ですが、産出域により特性が違うのが興味深いですね。
今日は市内で取付作業にお邪魔します。
今日も一日がんばりましょう‼
今日の木地ではセプターという材を取り上げたいと思います。

名称:セプター(マメ科)
広葉樹
地域:タイ、カンボジア、スマトラなど
引用(一財)日本木材総合情報センター
shindoraと分類される材とpseudosindoraと分類される種を総称し、セプターとして扱われています。
東南アジアを中心に生息し約20種ほどある種です。分布も広い為、産出国により名称も異なります。
樹種により芯材の色が異なる材で濃い赤褐色から、淡色桃色と色は様々です。
材としては木理は通直もしくは、若干交錯しており、加工性は少し良くないようで保存性は樹種により異なり材料の色が濃いほど重硬で保存性も高く、色が薄いほど軽軟で低いとされています。
フタバガキ科のラワンなどと木目に現れる樹脂道と呼ばれる細胞間道が同じように並んでいるのがshindoraに分類される種の特徴で他の材と見分けが容易です。
用途としては、家具などを中心にキャビネットなどに用いられ濃い色の縞が表面にあるものは装飾材として用いられているようです。
分布が複数国にまたがる材は、名称も様々でおもしろいです。
ほとんど扱うことのない材ですが、産出域により特性が違うのが興味深いですね。
今日は市内で取付作業にお邪魔します。
今日も一日がんばりましょう‼
2014年08月26日
今日の木地(スパニッシュシーダー)
おはようございます。今週はジメジメしたスタートになりましたが、今日はどんな天気になるんでしょうか??
さて、今日の木地ではスパニッシュシーダーという材を取り上げたいと思います。

名称:スパニッシュシーダー
広葉樹
地域:中南米
引用(一財)日本木材総合情報センター
名前はスパニッシュシダ―とありますがスペイン産のスギではありません。スギは針葉樹なのに対し、この材は広葉樹で全く違う種の材です。しかしこの材の芳香がシダ―に似たにおいがする為、こう呼ばれているようです。
その他、葉巻を収納する箱に用いられることから、シガーボックスシダ―とも呼ばれ知られています。
英名ではセドロと呼ばれているようです。
材は、熱帯材でありながら年輪がはっきりとしており、木理は通直で材は柔軟な為加工性に優れているようです。
材面は金色の光沢が現れるのが特徴です。耐久性が高く虫害も受けにくく材としての評価は良好です。
日本国内では建築、キャビネット、彫刻などに用いられているようです。
ただ、今現在はセドロの多くの個体はワシントン条約により輸出の制限・禁止とされているので材として見かけることは少なそうです。
以前流通があった材でこうした規制がかかってしまったことを知るのは、非常に残念です。
保護されることで何とか絶滅しないことを願いたいと思います。
さて、お盆以降予想以上に資材の流通が鈍っており、状況が少し悪いですが
今日も一日がんばりましょう‼
さて、今日の木地ではスパニッシュシーダーという材を取り上げたいと思います。

名称:スパニッシュシーダー
広葉樹
地域:中南米
引用(一財)日本木材総合情報センター
名前はスパニッシュシダ―とありますがスペイン産のスギではありません。スギは針葉樹なのに対し、この材は広葉樹で全く違う種の材です。しかしこの材の芳香がシダ―に似たにおいがする為、こう呼ばれているようです。
その他、葉巻を収納する箱に用いられることから、シガーボックスシダ―とも呼ばれ知られています。
英名ではセドロと呼ばれているようです。
材は、熱帯材でありながら年輪がはっきりとしており、木理は通直で材は柔軟な為加工性に優れているようです。
材面は金色の光沢が現れるのが特徴です。耐久性が高く虫害も受けにくく材としての評価は良好です。
日本国内では建築、キャビネット、彫刻などに用いられているようです。
ただ、今現在はセドロの多くの個体はワシントン条約により輸出の制限・禁止とされているので材として見かけることは少なそうです。
以前流通があった材でこうした規制がかかってしまったことを知るのは、非常に残念です。
保護されることで何とか絶滅しないことを願いたいと思います。
さて、お盆以降予想以上に資材の流通が鈍っており、状況が少し悪いですが
今日も一日がんばりましょう‼
2014年08月25日
今日の木地(シルバービーチ)
おはようございます。いよいよ八月最終週になりました。早いですね。
さて今日の木地では、シルバービーチという材を取り上げたいと思います。

名称:シルバービーチ(ブナ科)
広葉樹
地域:ニュージーランド
引用(一財)日本木材総合情報センター
樹高が30Mに達する材で、径は1.5M程になるようです。ビーチと付いていますが、実際はブナ類というよりガンバ類に近いようです。
材としては木理は通直で加工しやすく、肌目が細かく仕上がりが綺麗です。ただ耐久性が低く虫害を受けやすい面もありそういった部分を必要としない用途に用いられています。
主には、家具、床板、ろくろ細工、箱などに用いられているほか、ガンバ類が用いられる用途で代用として使われることが多いようです。
乾燥後の狂いが少ない材でそういった面では安定した材として使うことが出来ると思います。
ブナ科でもビーチは比較的よく扱うことがありますが、シルバービーチは扱ったことがなく、画像で見る限りでもビーチとは、似ていない印象です。
さて、今週はお天気どうでしょうか。
今日も一日がんばりましょう!!
さて今日の木地では、シルバービーチという材を取り上げたいと思います。

名称:シルバービーチ(ブナ科)
広葉樹
地域:ニュージーランド
引用(一財)日本木材総合情報センター
樹高が30Mに達する材で、径は1.5M程になるようです。ビーチと付いていますが、実際はブナ類というよりガンバ類に近いようです。
材としては木理は通直で加工しやすく、肌目が細かく仕上がりが綺麗です。ただ耐久性が低く虫害を受けやすい面もありそういった部分を必要としない用途に用いられています。
主には、家具、床板、ろくろ細工、箱などに用いられているほか、ガンバ類が用いられる用途で代用として使われることが多いようです。
乾燥後の狂いが少ない材でそういった面では安定した材として使うことが出来ると思います。
ブナ科でもビーチは比較的よく扱うことがありますが、シルバービーチは扱ったことがなく、画像で見る限りでもビーチとは、似ていない印象です。
さて、今週はお天気どうでしょうか。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年08月23日
今日の木地(ジョンコン)
おはようございます。一週間あっという間に過ぎますね。もう週末です。
さて今日の木地では、ジョンコンという材を取り上げたいと思います。
名称:ジョンコン(ノボタン科)
広葉樹
地域:ボルネオ、サラワク
引用(一財)日本木材総合情報センター
ボルネオ周辺の泥炭湿地帯にのみ成育しているようです。主には、家具の芯材などに用いられる材で完成品の化粧には使われない為、一般的にはあまり目に触れる機会は少ないと思います。
材としては、耐久性は低いものの、収縮、狂いが少なく虫害も受けにくいです。加工性も良く芯材として用いられる場合がほとんどです。ただ特有の孔と呼ばれる小さな穴が線香虫(正式名称が分かりません)などの虫穴に間違えられることも多く、あまり評価が良くありません。
そういった要因もあり、表面仕上げ材に用いられることはほとんどないと思います。
虫穴の様な穴はあるものの、実際には虫害は受けにくくそういった面では他の材に比べ評価は高いです。
個人の記憶ではこの材を挽く際に出る屑で手や腕がかゆくなった記憶が・・・資料にも繊維が皮膚炎などを起こすことがあるとあったので、この材を扱った際のことだと思います。
うちでも、以前は扱ったことがあるように思いますが、ここ最近はしばらく扱っていないと思います。
さてさて、土曜日ですが今日も張切っていきます。
今日も一日がんばりましょう!!
さて今日の木地では、ジョンコンという材を取り上げたいと思います。

名称:ジョンコン(ノボタン科)
広葉樹
地域:ボルネオ、サラワク
引用(一財)日本木材総合情報センター
ボルネオ周辺の泥炭湿地帯にのみ成育しているようです。主には、家具の芯材などに用いられる材で完成品の化粧には使われない為、一般的にはあまり目に触れる機会は少ないと思います。
材としては、耐久性は低いものの、収縮、狂いが少なく虫害も受けにくいです。加工性も良く芯材として用いられる場合がほとんどです。ただ特有の孔と呼ばれる小さな穴が線香虫(正式名称が分かりません)などの虫穴に間違えられることも多く、あまり評価が良くありません。
そういった要因もあり、表面仕上げ材に用いられることはほとんどないと思います。
虫穴の様な穴はあるものの、実際には虫害は受けにくくそういった面では他の材に比べ評価は高いです。
個人の記憶ではこの材を挽く際に出る屑で手や腕がかゆくなった記憶が・・・資料にも繊維が皮膚炎などを起こすことがあるとあったので、この材を扱った際のことだと思います。
うちでも、以前は扱ったことがあるように思いますが、ここ最近はしばらく扱っていないと思います。
さてさて、土曜日ですが今日も張切っていきます。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年08月22日
今日の木地(ジャラ)
おはようございます。気づけば八月も20日以上過ぎて、もう残すところ一週間ちょっとですね。
本当にあっという間です。
さて今日の木地では、ジャラという材を取り上げたいと思います。

名称:ジャラ(フトモモ科)
広葉樹
地域:オーストラリアなど
引用(一財)日本木材総合情報センター
数百あるユーカリの種の一つで、原産地であるオーストラリアでは、古くから装飾材として用いられています。
材としては、重硬で非常に重い材で耐久性も非常に高く評価されています。日本ではそういった特性を活かして杭や橋、枕木など耐久性、強度が必要とされる部分で用いられています。
その他、屋根、羽目板、ベニヤ材などに用いられています。
加工性はかなり難しいとあり、扱ったことはないものの切削中に煙が出て切削面を焦がすのが容易に想像つきます。また細かな仕上加工なども施工が難しいんではないかなという印象です。
ただ非常に耐久性が高く水の耐性も良いので、最近では屋外のデッキなどにも多く用いられているように思います。
加工品として扱うには、少し難しい材かもしれませんが用途によっては非常に特性を発揮し高耐久で維持できるメリットは、屋外や水気の多い箇所、用途には非常に向いていると思います。
さてさて月末も近くなり作業の日程も徐々に決まりつつあり、進行が楽しみです。
今日も一日がんばりましょう!!
本当にあっという間です。
さて今日の木地では、ジャラという材を取り上げたいと思います。

名称:ジャラ(フトモモ科)
広葉樹
地域:オーストラリアなど
引用(一財)日本木材総合情報センター
数百あるユーカリの種の一つで、原産地であるオーストラリアでは、古くから装飾材として用いられています。
材としては、重硬で非常に重い材で耐久性も非常に高く評価されています。日本ではそういった特性を活かして杭や橋、枕木など耐久性、強度が必要とされる部分で用いられています。
その他、屋根、羽目板、ベニヤ材などに用いられています。
加工性はかなり難しいとあり、扱ったことはないものの切削中に煙が出て切削面を焦がすのが容易に想像つきます。また細かな仕上加工なども施工が難しいんではないかなという印象です。
ただ非常に耐久性が高く水の耐性も良いので、最近では屋外のデッキなどにも多く用いられているように思います。
加工品として扱うには、少し難しい材かもしれませんが用途によっては非常に特性を発揮し高耐久で維持できるメリットは、屋外や水気の多い箇所、用途には非常に向いていると思います。
さてさて月末も近くなり作業の日程も徐々に決まりつつあり、進行が楽しみです。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年08月21日
今日の木地(なぜ集成材が普及しているのか?)
おはようございます。ここのところ非常に暑い日が続いています。体調管理気をつけないといけませんね。
さて、今日の木地では、なぜ集成材が普及しているのかを、取り上げたいと思います。
(個人の見解もところどころ入っていますのであしからず^^;)

【集成材:小さく刻まれた木を集めて形成したもの。板材、角材など材質によっても種類は無数にあります】
まず材としての面から。
・材質面
〈無垢材に比べ反り、狂いが少ない〉
集成材自体が小さく刻まれた木材の集まりで形成されているので、反り、狂いといった本来木の特性である欠点が 無垢材に比べ少なく、そのまま仕上げ材としも使用でき、既に板厚等は決まっているので製材(原木から板材に加 工)の手間時間も必要なく調達後 すぐさま製品加工出来るというメリットがあります。
・感触
〈小さい無垢材の集まり〉
無垢材の良さである触り心地や質感などは小さい無垢材の集まりなので本来の木にかなり近く、化粧合板などで
装飾したものとは違い非常に良い。
・強度
〈一部の角材などは無垢材に比べても強度的に強い〉
接合の技術、工法も以前に比べ格段に向上しており、建築用材では無垢材よりも強度が保たれているものもあり
製品としての信用度も向上しています。
・コスト面
〈手頃な価格で流通している〉
集成材でも材質により価格はまちまちですが、同じ寸法の無垢材を調達するのに比べ、非常に手頃な予算で流通 しているというのもメリットとしてあります。なぜ安価なのか…本来であれば材としては切り落とされてしまう部分も他 の材と使われることで材としての善し悪しは関係なく構成される為、無垢材では高価になってしまう大きさでも手軽 に手に入るんです。
・認知度
〈よく使われるようになり知っている人も増えている〉
昔であれば、やはり無垢材‼という方も多かったと思いますが、ここ最近は様々な部分で見かけるとも増え、デザイ ン、コンセプトの中に組み込まれていることもあり、認知度も高まり好きな人も増加しているように思います。
と、上げると諸々メリットは出てきますが、やはり何より無垢材が以前に比べ、良質で寸法の大きいものが少なくなっている現状から、対応策として用いられていることが一番の要因だと思います。
材として粗悪なものではないので、使用用途に応じて無垢材、集成材をうまく使い分けるのが最も良いのでは?と思います。
・・・というわけで今日も駿府匠宿 自由工房内にて木工体験教室やります‼
ご都合よろしければ、お立ち寄りくださいねm(__)m
さて、今日の木地では、なぜ集成材が普及しているのかを、取り上げたいと思います。
(個人の見解もところどころ入っていますのであしからず^^;)

【集成材:小さく刻まれた木を集めて形成したもの。板材、角材など材質によっても種類は無数にあります】
まず材としての面から。
・材質面
〈無垢材に比べ反り、狂いが少ない〉
集成材自体が小さく刻まれた木材の集まりで形成されているので、反り、狂いといった本来木の特性である欠点が 無垢材に比べ少なく、そのまま仕上げ材としも使用でき、既に板厚等は決まっているので製材(原木から板材に加 工)の手間時間も必要なく調達後 すぐさま製品加工出来るというメリットがあります。
・感触
〈小さい無垢材の集まり〉
無垢材の良さである触り心地や質感などは小さい無垢材の集まりなので本来の木にかなり近く、化粧合板などで
装飾したものとは違い非常に良い。
・強度
〈一部の角材などは無垢材に比べても強度的に強い〉
接合の技術、工法も以前に比べ格段に向上しており、建築用材では無垢材よりも強度が保たれているものもあり
製品としての信用度も向上しています。
・コスト面
〈手頃な価格で流通している〉
集成材でも材質により価格はまちまちですが、同じ寸法の無垢材を調達するのに比べ、非常に手頃な予算で流通 しているというのもメリットとしてあります。なぜ安価なのか…本来であれば材としては切り落とされてしまう部分も他 の材と使われることで材としての善し悪しは関係なく構成される為、無垢材では高価になってしまう大きさでも手軽 に手に入るんです。
・認知度
〈よく使われるようになり知っている人も増えている〉
昔であれば、やはり無垢材‼という方も多かったと思いますが、ここ最近は様々な部分で見かけるとも増え、デザイ ン、コンセプトの中に組み込まれていることもあり、認知度も高まり好きな人も増加しているように思います。
と、上げると諸々メリットは出てきますが、やはり何より無垢材が以前に比べ、良質で寸法の大きいものが少なくなっている現状から、対応策として用いられていることが一番の要因だと思います。
材として粗悪なものではないので、使用用途に応じて無垢材、集成材をうまく使い分けるのが最も良いのでは?と思います。
・・・というわけで今日も駿府匠宿 自由工房内にて木工体験教室やります‼

ご都合よろしければ、お立ち寄りくださいねm(__)m
2014年08月20日
今日の木地(ジェルトン)
おはようございます。ここのところとても暑い日が続いてます・・・予定も目いっぱいですが張切っていこうと思います。
さて今日の木地では、ジェルトンという材を取り上げたいと思います。
名称:ジェルトン(キョウチクトウ科)
広葉樹
地域:ボルネオ、マレーシア半島など
引用(一財)日本木材総合情報センター
乾燥地帯に自生していることが多く、木材はプライという材に非常によく似ている為、見違えることも多いようです。
樹自体は樹高60M、径2.5Mほどにもなる大きな樹です。
製材乾燥は容易なものの、保存性が低く乾燥中にカビの害や虫害を受けることもあるそうで要注意な材のようです。
材としては板目に大きな孔(穴など)が出てしまい、保存性も低く、あまり強度もない為、材としては低く評価されています。しかし加工、切削などはしやすいので、主には芯材や集成材など直接仕上げに関係がない部分で使われています。
日本国内ではあまりなじみのある材ではない様ですが、この樹から採取される乳液がガム原料であるのチクルで、多く採取されている為、実は知らないところでこの種と関わっていると思います。
資料ではあまりなかったですが、木製の模型などは柔らかく加工がしやすいのでこの材などが用いられるとがある印象です。
今日は明日のイベントの準備などをしたいと思います。
今日も一日がんばりましょう!!
さて今日の木地では、ジェルトンという材を取り上げたいと思います。

名称:ジェルトン(キョウチクトウ科)
広葉樹
地域:ボルネオ、マレーシア半島など
引用(一財)日本木材総合情報センター
乾燥地帯に自生していることが多く、木材はプライという材に非常によく似ている為、見違えることも多いようです。
樹自体は樹高60M、径2.5Mほどにもなる大きな樹です。
製材乾燥は容易なものの、保存性が低く乾燥中にカビの害や虫害を受けることもあるそうで要注意な材のようです。
材としては板目に大きな孔(穴など)が出てしまい、保存性も低く、あまり強度もない為、材としては低く評価されています。しかし加工、切削などはしやすいので、主には芯材や集成材など直接仕上げに関係がない部分で使われています。
日本国内ではあまりなじみのある材ではない様ですが、この樹から採取される乳液がガム原料であるのチクルで、多く採取されている為、実は知らないところでこの種と関わっていると思います。
資料ではあまりなかったですが、木製の模型などは柔らかく加工がしやすいのでこの材などが用いられるとがある印象です。
今日は明日のイベントの準備などをしたいと思います。
今日も一日がんばりましょう!!