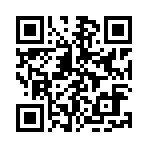2014年06月30日
今日の木地(クリンキパイン)
おはようございます。今日で六月も終わりですね。今月は本当にあっという間でした。
来月はどんな月になるんでしょうか??楽しみです。
さて、今日の木地では、クリンキパインを紹介したいと思います。
名称:クリンキパイン(ナンヨウスギ科)
針葉樹
地域:パプアニューギニア
引用(一財)日本木材総合情報センター
パインと名がつくのですが、ナンヨウスギ科の種です。しかし、国内のマツ・スギなどと全く関連のない種だそうです。紛らわしいですね・・・。立木の姿は、マツ科の種に似ているようです。資料にもありましたが画像の通り、アガチスに非常によく似ているようです。もしかしたらアガチスとして扱ったことがあるのかも!?と思うほど似ている印象ですが、原木で国内に入ってくることはまずないようです。
と言うのも、この種は現地、その周辺で合板や製品に加工され出回ることがほとんどだそうです。
用途としては、家具、合板、木型、マッチ柄、割りばしなどに用いられるそうです。
クリンキパインという名の材は扱ったことがないんですが、流量は比較的多いようです。知らずして扱っている材でしょうか??
外材は種により、ごく数年で流量が極端に少なくなったり、呼び名が変わったり割と激しいように思うんですが、
この種の名前は聞いたことがありませんでした。
外材は、扱う機会はかなり増えていますが、産地によっても全然違う種の様な材も多いのであまりよくわかりません。
名前の横文字の様な名前なので覚えにくいです・・・
さて今日は、清水方面にお邪魔します。外工事なので雨が降らないといいんですが。
今日も一日がんばりましょう!!
来月はどんな月になるんでしょうか??楽しみです。
さて、今日の木地では、クリンキパインを紹介したいと思います。

名称:クリンキパイン(ナンヨウスギ科)
針葉樹
地域:パプアニューギニア
引用(一財)日本木材総合情報センター
パインと名がつくのですが、ナンヨウスギ科の種です。しかし、国内のマツ・スギなどと全く関連のない種だそうです。紛らわしいですね・・・。立木の姿は、マツ科の種に似ているようです。資料にもありましたが画像の通り、アガチスに非常によく似ているようです。もしかしたらアガチスとして扱ったことがあるのかも!?と思うほど似ている印象ですが、原木で国内に入ってくることはまずないようです。
と言うのも、この種は現地、その周辺で合板や製品に加工され出回ることがほとんどだそうです。
用途としては、家具、合板、木型、マッチ柄、割りばしなどに用いられるそうです。
クリンキパインという名の材は扱ったことがないんですが、流量は比較的多いようです。知らずして扱っている材でしょうか??
外材は種により、ごく数年で流量が極端に少なくなったり、呼び名が変わったり割と激しいように思うんですが、
この種の名前は聞いたことがありませんでした。
外材は、扱う機会はかなり増えていますが、産地によっても全然違う種の様な材も多いのであまりよくわかりません。
名前の横文字の様な名前なので覚えにくいです・・・
さて今日は、清水方面にお邪魔します。外工事なので雨が降らないといいんですが。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月28日
今日の木地(マツ科に属する材)
おはようございます。昨日は一現場無事に完了を迎え、ホッと一安心しました♪
さて今日の木地です。今日はマツ科の材を紹介したいと思います。
(サザンイエローパイン)
(北洋カラマツ)
引用(一財)日本木材総合情報センター
マツ科のほとんどの種は、北半球で生産されるようです。上記画像は、うちでもよく扱いのある種を掲載しましたが、
まだまだすごい数の種類に分類されているようです。種により木目などはそれぞれですが、どれも木目は、マツ独特の特徴的なものです。
材としてはほとんどの種が、脂があり水に強く建築材、家具・建具材、その他電柱や丸太のまま用いたり、
彫刻、器具などにも用いられています。
種によりほとんどがパルプの原料になったり、合板の材料になる種もあります。
ほとんどが北半球で育つのは知りませんでした。寒い方が良く育つのでしょうか??成育環境も興味深いですね。
さてさて、今日は私用もありこっそり半休をもらう予定です♪ただ…半休を頂いた日はなぜか電話が鳴りやまなくなるので少し怖いんですが(笑)
今月もあとちょっとですね。今日も一日がんばりましょう!!
さて今日の木地です。今日はマツ科の材を紹介したいと思います。

(サザンイエローパイン)

(北洋カラマツ)
引用(一財)日本木材総合情報センター
マツ科のほとんどの種は、北半球で生産されるようです。上記画像は、うちでもよく扱いのある種を掲載しましたが、
まだまだすごい数の種類に分類されているようです。種により木目などはそれぞれですが、どれも木目は、マツ独特の特徴的なものです。
材としてはほとんどの種が、脂があり水に強く建築材、家具・建具材、その他電柱や丸太のまま用いたり、
彫刻、器具などにも用いられています。
種によりほとんどがパルプの原料になったり、合板の材料になる種もあります。
ほとんどが北半球で育つのは知りませんでした。寒い方が良く育つのでしょうか??成育環境も興味深いですね。
さてさて、今日は私用もありこっそり半休をもらう予定です♪ただ…半休を頂いた日はなぜか電話が鳴りやまなくなるので少し怖いんですが(笑)
今月もあとちょっとですね。今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月27日
今日の木地(アガチス)
おはようございます。金曜日です。今週もの怒涛スケジュールでした…。雨は降りましたが、幸運にも作業には支障がなくどれも予定通り進みホット一安心です。
さて、木地録もいよいよ外材に突入です。今日はアガチスを紹介したいと思います。

名称:アガチス(ナンヨウスギ科)
針葉樹
地域:東南アジア、ニュージーランド
引用(一財)日本木材総合情報センター
外材です。既に家具、建具材としては非常になじみのある材です。以前紹介したカツラの代用材として流通しています。
材としては、木肌は細かく加工性はとても良いです。ただ、アテ材は狂いが非常に激しく、乾燥製品後も大きく狂います。用途としては、家具、建具材に用いられ、特に抽斗材は無垢板ならアガチスと言っていいほど主流になっています。ドア枠、装飾材の塗装下地などにも多用されます。木肌がおとなしいのでめつぶし塗装の仕上がりがとてもきれいです。
比較的万能な材料だと思います。しかし、水に弱く、打撃などにも弱い為、耐朽が求められる用途には向きません。
うちでも以前より、他の材に比べると多くの板材を在庫しています。この材は重宝な為加工する際、まとまった量で出るのが一番の要因です。なので厚み違いで複数の板材を在庫しています。
こうした在庫のおかげでとにかく急ぎで!!と言ったご要望の際も、スムーズに着手出来るんです。
さてさて、今日は、いよいよ一現場が完了引き渡しを迎えます。なんだかうれしいような、少しさみしいような…
とにかく完了までがんばって施工したいと思います。
今日も一日がんばりましょう!!
さて、木地録もいよいよ外材に突入です。今日はアガチスを紹介したいと思います。

名称:アガチス(ナンヨウスギ科)
針葉樹
地域:東南アジア、ニュージーランド
引用(一財)日本木材総合情報センター
外材です。既に家具、建具材としては非常になじみのある材です。以前紹介したカツラの代用材として流通しています。
材としては、木肌は細かく加工性はとても良いです。ただ、アテ材は狂いが非常に激しく、乾燥製品後も大きく狂います。用途としては、家具、建具材に用いられ、特に抽斗材は無垢板ならアガチスと言っていいほど主流になっています。ドア枠、装飾材の塗装下地などにも多用されます。木肌がおとなしいのでめつぶし塗装の仕上がりがとてもきれいです。
比較的万能な材料だと思います。しかし、水に弱く、打撃などにも弱い為、耐朽が求められる用途には向きません。
うちでも以前より、他の材に比べると多くの板材を在庫しています。この材は重宝な為加工する際、まとまった量で出るのが一番の要因です。なので厚み違いで複数の板材を在庫しています。
こうした在庫のおかげでとにかく急ぎで!!と言ったご要望の際も、スムーズに着手出来るんです。
さてさて、今日は、いよいよ一現場が完了引き渡しを迎えます。なんだかうれしいような、少しさみしいような…
とにかく完了までがんばって施工したいと思います。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月26日
今日の木地(道具のあれこれ その1)
おはようございます。やはり晴れ男なんでしょうか??
昨日は、外作業が終わった途端雨が降りました。それまでは日差しも強く暑い陽気だったんですが。
作業が順調に終えられたので助かりました。
さて今日の木地です。今日は木曜日なので関連する用語を紹介します!!
今日は道具の名称と用途などを紹介したいと思います。
木を扱う職人さんでも職種により様々ですが、僕が普段から使っている木を加工する道具を取り上げていきたいと思います。
まずは・・・
【鉋(かんな)】
材を仕上る際に使います。鉋の中にも、おおまかに削る荒仕子(あらしこ)、並々に仕上る(中仕子)、などなど同じ削る用途でも段階に応じた鉋を使います。鉋自体に決まりはないんですが、鋼の良いものほど、大切にしたいので本当の仕上げの時にしか使わない。など少しこだわりに近いものかもしれません。
その他、Lの字の隅を削る際(きわ)鉋や、シャクリ鉋、面取り鉋など加工する用途により種類はものすごく豊富にあります。
僕が日常使っているもので最低限で5~6種類と言ったところです。
最近は替え刃式と言う近代的なものもありますが、僕自身自分の研ぎ調子で仕上げたいのでほとんど使ったことがありません。
【鋸(のこぎり)】
鋸には、刃の荒い縦引き(繊維と平行に刻む)用と横引き(繊維と垂直に刻む)用があります。一般の方が、想像する表裏に刃の付いているタイプの物は、目立て職人さんが町から激減し、急激に疎遠になっています。
と言うのも、刃自体が頻繁に切れなくなるうえ、替え刃が非常に安価で流通しているのも要因の一つです。
鋸に関してはほぼ、替え刃が主流になっています。
鋸の最大の敵は鉄です。材料を挽いている際、ステープル(ホッチキスのタマ)や、釘、ビスと言ったものが状況により刺さってしまっていることがあり、これを知らずに切ってしまうと…刃はすぐさま切れなくなってしまします。
造作中など、隣で作業をしている職人が鋸を使っていて音が変わる瞬間があります。「あ。。拾ってしまったな・・・」とすぐわかります。
既に材の中に埋もれていると予測が困難でよく職人を泣かせる天敵です。
【鑿(のみ)】
いまだにこの漢字、書けません。通常の職人さんであれば、平型の叩き鑿の幅の細いものから太いものの組合せを持っています。10本組が主流でしょうか。ほりたいほず(組手を差し込む穴)の幅に合わせチョイスします。
ほり幅めいっぱいの鑿を突き初めから使うと必ず失敗します。なぜなら、木には繊維方向、目通りなどあり、木質により本来刻みたいヶ所の廻りも引っ張ってきてしまいます。その為突き初めは一回り小さい鑿で繊維を断つように刻みます。この辺の手加減は材種により異なりますが、ほぼ感触と手加減で調整していきます。一突きで硬くも緩くもなってしまうので慎重な作業になります。とにかく良く切れることが大前提です。
【毛引き(けひき)】
刻む前に印をつける道具です。この道具には先端に鋼が付いているので表面の繊維を予め切っておき仕上げを綺麗にするといった使い方が出来ます。付属の盤が定規になり、複数の隅付けもスムーズに行えます。専門的な使い勝手もあるんですがここでは簡単に紹介させてもらいます。
【玄能(げんのう)】
カナヅチのことですが、昔から玄能と呼んでいます。こちらも丸型、角型など形状の種類はありますが、僕の玄能は
打撃面が片側が平でもう片側が丸と言うタイプの物を使っています。
職種により片側がバール形状になっているものを使っている職人さんもいます。
うちの職では、おおむね60~80匁(225~300g)程度の物を皆使っていますが、個人的には100匁(375g)の物が重みもあり、使いやすく愛用しています。その為人に貸すと重いといわれます・・・
今回は刃物を中心に紹介しました。どれもただ扱うだけではなかなかうまく扱えないものですが、日頃から使い慣れた道具は、調子もよくわかり仕上も読めます。こういった部分は、木を扱う職ならではかもしれませんね。
張切って画像も用意したんですが…うまく添付できなかったのでまたの機会に。
今日は、市内を転々と施工して廻ります。順調に進むんでしょうか??
それでは今日も一日がんばりましょう!!
昨日は、外作業が終わった途端雨が降りました。それまでは日差しも強く暑い陽気だったんですが。
作業が順調に終えられたので助かりました。
さて今日の木地です。今日は木曜日なので関連する用語を紹介します!!
今日は道具の名称と用途などを紹介したいと思います。
木を扱う職人さんでも職種により様々ですが、僕が普段から使っている木を加工する道具を取り上げていきたいと思います。
まずは・・・
【鉋(かんな)】
材を仕上る際に使います。鉋の中にも、おおまかに削る荒仕子(あらしこ)、並々に仕上る(中仕子)、などなど同じ削る用途でも段階に応じた鉋を使います。鉋自体に決まりはないんですが、鋼の良いものほど、大切にしたいので本当の仕上げの時にしか使わない。など少しこだわりに近いものかもしれません。
その他、Lの字の隅を削る際(きわ)鉋や、シャクリ鉋、面取り鉋など加工する用途により種類はものすごく豊富にあります。
僕が日常使っているもので最低限で5~6種類と言ったところです。
最近は替え刃式と言う近代的なものもありますが、僕自身自分の研ぎ調子で仕上げたいのでほとんど使ったことがありません。
【鋸(のこぎり)】
鋸には、刃の荒い縦引き(繊維と平行に刻む)用と横引き(繊維と垂直に刻む)用があります。一般の方が、想像する表裏に刃の付いているタイプの物は、目立て職人さんが町から激減し、急激に疎遠になっています。
と言うのも、刃自体が頻繁に切れなくなるうえ、替え刃が非常に安価で流通しているのも要因の一つです。
鋸に関してはほぼ、替え刃が主流になっています。
鋸の最大の敵は鉄です。材料を挽いている際、ステープル(ホッチキスのタマ)や、釘、ビスと言ったものが状況により刺さってしまっていることがあり、これを知らずに切ってしまうと…刃はすぐさま切れなくなってしまします。
造作中など、隣で作業をしている職人が鋸を使っていて音が変わる瞬間があります。「あ。。拾ってしまったな・・・」とすぐわかります。
既に材の中に埋もれていると予測が困難でよく職人を泣かせる天敵です。
【鑿(のみ)】
いまだにこの漢字、書けません。通常の職人さんであれば、平型の叩き鑿の幅の細いものから太いものの組合せを持っています。10本組が主流でしょうか。ほりたいほず(組手を差し込む穴)の幅に合わせチョイスします。
ほり幅めいっぱいの鑿を突き初めから使うと必ず失敗します。なぜなら、木には繊維方向、目通りなどあり、木質により本来刻みたいヶ所の廻りも引っ張ってきてしまいます。その為突き初めは一回り小さい鑿で繊維を断つように刻みます。この辺の手加減は材種により異なりますが、ほぼ感触と手加減で調整していきます。一突きで硬くも緩くもなってしまうので慎重な作業になります。とにかく良く切れることが大前提です。
【毛引き(けひき)】
刻む前に印をつける道具です。この道具には先端に鋼が付いているので表面の繊維を予め切っておき仕上げを綺麗にするといった使い方が出来ます。付属の盤が定規になり、複数の隅付けもスムーズに行えます。専門的な使い勝手もあるんですがここでは簡単に紹介させてもらいます。
【玄能(げんのう)】
カナヅチのことですが、昔から玄能と呼んでいます。こちらも丸型、角型など形状の種類はありますが、僕の玄能は
打撃面が片側が平でもう片側が丸と言うタイプの物を使っています。
職種により片側がバール形状になっているものを使っている職人さんもいます。
うちの職では、おおむね60~80匁(225~300g)程度の物を皆使っていますが、個人的には100匁(375g)の物が重みもあり、使いやすく愛用しています。その為人に貸すと重いといわれます・・・
今回は刃物を中心に紹介しました。どれもただ扱うだけではなかなかうまく扱えないものですが、日頃から使い慣れた道具は、調子もよくわかり仕上も読めます。こういった部分は、木を扱う職ならではかもしれませんね。
張切って画像も用意したんですが…うまく添付できなかったのでまたの機会に。
今日は、市内を転々と施工して廻ります。順調に進むんでしょうか??
それでは今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月25日
今日の木地(クワ)
おはようございます。昨日は夕方局地的な雨に見事に降られすさまじかったです。
ゲリラ豪雨ですね。ホントに。
さて今日の木地はクワを紹介したいと思います。
国産の材は今回のクワでいったん終了です。

名称:クワ(クワ科)
落葉樹
地域:北海道~沖縄
引用(一財)日本木材総合情報センター
非常に流量の少ない材です。扱ったないです。肌目が粗い材の様ですが、特徴的な杢が出ることでしられているようです。昔から和家具などによく用いられていた材で、昔は比較的触れる機会が多かったようです。
中国が原産で養蚕用として用いられていることも有名です。
材としては加工性は、低く硬い材のようですが、仕上がり面は綺麗で保存性も良いようです。
現在はほとんど、流通してないないように思います。あまり採取されていないのかもしれません。
この種は果樹としてもよく知られているみたいですね。
母親が、この種の果実を幼少の頃よく食べていたという話をよく聞いたのを思い出しました。それにまつわる面白エピソードもあったと思いました(笑)
さて、今日はお天気によって予定が流動的になりそうですが…昨日のような強い雨が降ると本当に困ってしまいます。
今日も一日頑張りましょう。
ゲリラ豪雨ですね。ホントに。
さて今日の木地はクワを紹介したいと思います。
国産の材は今回のクワでいったん終了です。

名称:クワ(クワ科)
落葉樹
地域:北海道~沖縄
引用(一財)日本木材総合情報センター
非常に流量の少ない材です。扱ったないです。肌目が粗い材の様ですが、特徴的な杢が出ることでしられているようです。昔から和家具などによく用いられていた材で、昔は比較的触れる機会が多かったようです。
中国が原産で養蚕用として用いられていることも有名です。
材としては加工性は、低く硬い材のようですが、仕上がり面は綺麗で保存性も良いようです。
現在はほとんど、流通してないないように思います。あまり採取されていないのかもしれません。
この種は果樹としてもよく知られているみたいですね。
母親が、この種の果実を幼少の頃よく食べていたという話をよく聞いたのを思い出しました。それにまつわる面白エピソードもあったと思いました(笑)
さて、今日はお天気によって予定が流動的になりそうですが…昨日のような強い雨が降ると本当に困ってしまいます。
今日も一日頑張りましょう。
2014年06月24日
今日の木地(ヤチダモ)
おはようございます。昨日も怪しい天気でしたが暑い一日でした。
今日はどうでしょうか??
さて、今日の木地では、ヤチダモを紹介します。

名称:ヤチダモ(モクセイ科)
落葉樹
地域:北海道~本州
引用(一財)日本木材総合情報センター
この木地録の中でも、アオダモ、アカダモと紹介してきましたが、今回のヤチダモはモクセイ科に属し、性質としてはアオダモに近いと思います(アカダモはニレ科なので)しかし画像のように、木肌はアカダモのように道管があり見た目はアカダモに近い気がします。
材としてはアオダモがバットの材料に用いられることで有名なように、木製のテニスラケットはほとんどがこの材が用いられていたようです。
その他、家具や器具、合板などに用いられることが多く、内装材として用いられています。
実際の物流では、製品として板材になっていると、少し色目が違うなどその程度で内装装飾材としては、○○タモといったようにあまり区別されることは少ない印象です。
ブナ科の材と同様に成長が良いほど、重硬な材になる傾向でこの辺の特徴は、広葉樹は全般そうかもしれません。
実際はまだまだ無数に存在すると思いますが、国産の材の紹介も残り少なくなってきました。
こうしてみると、属する種によって特徴も様々でとても面白いです。
さて、今日は市内のお宅で作業をします。少し頭を使う作業なのでしっかり考えながら進めていきたいと思います。
今日も一日がんばりましょう!!
今日はどうでしょうか??
さて、今日の木地では、ヤチダモを紹介します。

名称:ヤチダモ(モクセイ科)
落葉樹
地域:北海道~本州
引用(一財)日本木材総合情報センター
この木地録の中でも、アオダモ、アカダモと紹介してきましたが、今回のヤチダモはモクセイ科に属し、性質としてはアオダモに近いと思います(アカダモはニレ科なので)しかし画像のように、木肌はアカダモのように道管があり見た目はアカダモに近い気がします。
材としてはアオダモがバットの材料に用いられることで有名なように、木製のテニスラケットはほとんどがこの材が用いられていたようです。
その他、家具や器具、合板などに用いられることが多く、内装材として用いられています。
実際の物流では、製品として板材になっていると、少し色目が違うなどその程度で内装装飾材としては、○○タモといったようにあまり区別されることは少ない印象です。
ブナ科の材と同様に成長が良いほど、重硬な材になる傾向でこの辺の特徴は、広葉樹は全般そうかもしれません。
実際はまだまだ無数に存在すると思いますが、国産の材の紹介も残り少なくなってきました。
こうしてみると、属する種によって特徴も様々でとても面白いです。
さて、今日は市内のお宅で作業をします。少し頭を使う作業なのでしっかり考えながら進めていきたいと思います。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月23日
今日の木地(ミズナラ)
おはようございます。6月も後半戦突入です。今月はまだまだスケジュールがいっぱいです♪
一つずつしっかり完了していきたいです!!
さて、今日の木地ではミズナラを紹介したいと思います。
名称:ミズナラ(ブナ科)
落葉樹
地域:北海道~九州
引用(一財)日本木材総合情報センター
この種のほとんどが北海道産です。欧米などでも家具などに多く用いられている種で、国内でも最近は需要があるようです。
材としては、硬い材と比較的やわらかい材と分かれるようですが、これは成長過程の良し悪しが要因で分かれ、成長が良いと比重が高く硬くなり、悪いと柔軟な材になるようです。
ナラ系の材には、トラフと呼ばれる帯状の模様がでます。この模様も人気の一つになっています。
用途としては家具、器具、床材、造船、木炭、合板などのほか、ウィスキーの樽に使われる材で、海外の樽もこの種の材で出来ており、樽には欠かせない材です。
北海道産の材はジャパニーズオークとして海外でも良質として扱われ、輸出も盛んにされているようです。
僕の知る限りでは、ナラと区別されている印象はないんですが、用途などははっきりと分かれているのを初めて知りました。
さて、週末は家族で出かけ、たくさん遊んできたんで今週も張切ってがんばっていこうと思います!!
今日も一日がんばりましょう!!
一つずつしっかり完了していきたいです!!
さて、今日の木地ではミズナラを紹介したいと思います。

名称:ミズナラ(ブナ科)
落葉樹
地域:北海道~九州
引用(一財)日本木材総合情報センター
この種のほとんどが北海道産です。欧米などでも家具などに多く用いられている種で、国内でも最近は需要があるようです。
材としては、硬い材と比較的やわらかい材と分かれるようですが、これは成長過程の良し悪しが要因で分かれ、成長が良いと比重が高く硬くなり、悪いと柔軟な材になるようです。
ナラ系の材には、トラフと呼ばれる帯状の模様がでます。この模様も人気の一つになっています。
用途としては家具、器具、床材、造船、木炭、合板などのほか、ウィスキーの樽に使われる材で、海外の樽もこの種の材で出来ており、樽には欠かせない材です。
北海道産の材はジャパニーズオークとして海外でも良質として扱われ、輸出も盛んにされているようです。
僕の知る限りでは、ナラと区別されている印象はないんですが、用途などははっきりと分かれているのを初めて知りました。
さて、週末は家族で出かけ、たくさん遊んできたんで今週も張切ってがんばっていこうと思います!!
今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月21日
今日の木地(マカンバ)
おはようございます。週末ですね。今週もとっても内容の濃い一週間になりました。
来週完成予定の現場も、とても順調でいよいよ引渡と言ったところです。
さて、今日の木地です。今日はマカンバを紹介します。

名称:マカンバ
落葉樹
地域:北海道~本州
引用(一財)日本木材総合情報センター
カバノキ科に属す材です。ほとんどの場合ミズメザクラとして流通していますが、画像を見る限りでは、ミズメとして流通しているものと少し木肌が異なるように思います。
どうやら明治時代頃からサクラと呼ばれ流通していたようです。材としては若干硬めで体育館の床材などによく用いられているようです。
家具・建築内装材としては比較的高級な材で流通しています。
体育館のほか、器具や合板、靴の木型なんかにも用いられているようです。
耐摩擦性が高い材でその特徴を活かした用途に使われることが多いようです。
僕の道具箱は、この職場に戻って2年ちょっと経った頃、ミズメを使って自分で造りましたが、おそらくマカンバなのだと思います。もう9年ちょっと使っていますが、まだまだ役割を果たして仕事してくれそうです。
少々強めな扱いにもびくともしません!!駆け出しの頃でしたがしっかりと造ったのでものすごく愛着があります。
実は特性を活かした材料選びだったのかもしれません。その当時は全然わからなかったですが…
さて、今日は清水の方に伺い一日外で作業します。
今日も一日がんばりましょう!!
来週完成予定の現場も、とても順調でいよいよ引渡と言ったところです。
さて、今日の木地です。今日はマカンバを紹介します。

名称:マカンバ
落葉樹
地域:北海道~本州
引用(一財)日本木材総合情報センター
カバノキ科に属す材です。ほとんどの場合ミズメザクラとして流通していますが、画像を見る限りでは、ミズメとして流通しているものと少し木肌が異なるように思います。
どうやら明治時代頃からサクラと呼ばれ流通していたようです。材としては若干硬めで体育館の床材などによく用いられているようです。
家具・建築内装材としては比較的高級な材で流通しています。
体育館のほか、器具や合板、靴の木型なんかにも用いられているようです。
耐摩擦性が高い材でその特徴を活かした用途に使われることが多いようです。
僕の道具箱は、この職場に戻って2年ちょっと経った頃、ミズメを使って自分で造りましたが、おそらくマカンバなのだと思います。もう9年ちょっと使っていますが、まだまだ役割を果たして仕事してくれそうです。
少々強めな扱いにもびくともしません!!駆け出しの頃でしたがしっかりと造ったのでものすごく愛着があります。
実は特性を活かした材料選びだったのかもしれません。その当時は全然わからなかったですが…
さて、今日は清水の方に伺い一日外で作業します。
今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月20日
今日の木地(ホウノキ)
おはようございます。昨日もすごくお天気に恵まれ自分が外仕事を組んでいる日はここ数週間ほぼ晴れ、晴れ男に格上げされたようで!?と思いこんでいます。各現場の方も、ほぼ問題なく進行中で一安心♪と言ったところですが、現場作業は最後までなにが起こるか分からないので、あと少し気を張っていきたいと思います。
はて、今日の木地です。今日はホオノキを紹介したいと思います。

名称:ホオノキ(モクレン科)
落葉樹
地域:北海道~沖縄
引用(一財)日本木材総合情報センター
扱ったことのない種です。材としては狂いも少なく軽軟で木肌も良い木のようです。広葉樹でここまで穏やかに評価される材もあまりない印象です。
用途は、特徴を活かした加工にむいていて、彫刻・機械・箱・内装・器具と言った比較的細かな精度の高いものに多く用いられているようです。
その他、他の材に比べヤニが少なく刃物の柄に用いられたり、下駄の歯やまな板といった用途もよく知られています。
材としての特徴ではありませんが、葉には殺菌作用があり食材を包んだり、載せたりして食器の代わりに使われたりしているようです。殺菌作用と言うものが個人的には不思議でしょうがいないんですが、木にはこういった特性をもった種がいくつかあり、とても興味深いです。
さて、今日は前々から気になっていました収納に関する研修に参加します♪
今日も一日がんばりましょう!!
はて、今日の木地です。今日はホオノキを紹介したいと思います。

名称:ホオノキ(モクレン科)
落葉樹
地域:北海道~沖縄
引用(一財)日本木材総合情報センター
扱ったことのない種です。材としては狂いも少なく軽軟で木肌も良い木のようです。広葉樹でここまで穏やかに評価される材もあまりない印象です。
用途は、特徴を活かした加工にむいていて、彫刻・機械・箱・内装・器具と言った比較的細かな精度の高いものに多く用いられているようです。
その他、他の材に比べヤニが少なく刃物の柄に用いられたり、下駄の歯やまな板といった用途もよく知られています。
材としての特徴ではありませんが、葉には殺菌作用があり食材を包んだり、載せたりして食器の代わりに使われたりしているようです。殺菌作用と言うものが個人的には不思議でしょうがいないんですが、木にはこういった特性をもった種がいくつかあり、とても興味深いです。
さて、今日は前々から気になっていました収納に関する研修に参加します♪
今日も一日がんばりましょう!!
2014年06月19日
今日の木地(目なり、習い目、逆目)
おはようございます。昨日は降ったりやんだりのはっきりしない天気でいよいよ梅雨かな??と言った天気でしたね。
今日はどうでしょうか!?外作業があるので出来れば降らないでもらえると助かるんですが…
さて、今日の木地です。木曜ですので用語について紹介したいと思います。
今日は仕上の際に出る【習い目(ならいめ)】・【逆目(さかめ)】を紹介します。
木にはそれぞれ目の方向により性質が異なり、材になった時の削り方向や角度なんかにより
仕上がり方が変わってきます。
【ならい目】
削る際に繊維方向をなでるように、削ることを指す言葉です。
左の図のように削ることで繊維は目起きと言い木肌のけば立ちを防ぎ、光沢のあるとてもきれいな仕上がりとなります。
【逆目(さかめ)】
ならい目とは逆に繊維に対し、一直線・繊維刺さるように削ることを指します。
左の図の様な方向で削った場合、木肌はけば立ちや材自体を引っ張り裂いたような荒らしい仕上りになり光沢もほとんど出ません。
こういったように目通りの良い材程、ならい目、逆目ははっきりとしていて明らかになります。
材の中には目通りの落ち着かないアテと呼ばれる部位もありますが、その部位に関しては数センチ刻みで目方向も変わり仕上面にばらつきが出やすいです。
場合によっては逆目とわかっていても仕方なく仕上げなければならない場合もあります。その為に仕上機(かんなの役割を果たす機械)やカンナには裏座と呼ばれる主たる刃の内側にあるものを調整し、極力仕上面を荒らさないようにします。
超仕上と言ったような仕上の場合、その都度、刃がねの研ぎや調整、台直しなど入念にして仕上ます。
そこまで仕上げる材は目通りも良いものが多いんですが。
今ではサンドペーパーの様な研磨して仕上る方法もありますが、やはり生地の仕上はよく切れた鉋で仕上げた光沢の綺麗さにはかないません。昔から叩き込まれた基礎かもしれませんがベテランの職人さんは削るときに出る屑ですら、綺麗な出方などこだわりを持っています。
それくらい仕上げに関してはより綺麗に!といった思いも強いです。
道具の専門的な部分も少し出ましたが、そちらに関してはまたの機会に。
それでは今日も一日がんばりましょう!!
今日はどうでしょうか!?外作業があるので出来れば降らないでもらえると助かるんですが…
さて、今日の木地です。木曜ですので用語について紹介したいと思います。
今日は仕上の際に出る【習い目(ならいめ)】・【逆目(さかめ)】を紹介します。
木にはそれぞれ目の方向により性質が異なり、材になった時の削り方向や角度なんかにより
仕上がり方が変わってきます。
【ならい目】
削る際に繊維方向をなでるように、削ることを指す言葉です。
左の図のように削ることで繊維は目起きと言い木肌のけば立ちを防ぎ、光沢のあるとてもきれいな仕上がりとなります。
【逆目(さかめ)】
ならい目とは逆に繊維に対し、一直線・繊維刺さるように削ることを指します。
左の図の様な方向で削った場合、木肌はけば立ちや材自体を引っ張り裂いたような荒らしい仕上りになり光沢もほとんど出ません。
こういったように目通りの良い材程、ならい目、逆目ははっきりとしていて明らかになります。
材の中には目通りの落ち着かないアテと呼ばれる部位もありますが、その部位に関しては数センチ刻みで目方向も変わり仕上面にばらつきが出やすいです。
場合によっては逆目とわかっていても仕方なく仕上げなければならない場合もあります。その為に仕上機(かんなの役割を果たす機械)やカンナには裏座と呼ばれる主たる刃の内側にあるものを調整し、極力仕上面を荒らさないようにします。
超仕上と言ったような仕上の場合、その都度、刃がねの研ぎや調整、台直しなど入念にして仕上ます。
そこまで仕上げる材は目通りも良いものが多いんですが。
今ではサンドペーパーの様な研磨して仕上る方法もありますが、やはり生地の仕上はよく切れた鉋で仕上げた光沢の綺麗さにはかないません。昔から叩き込まれた基礎かもしれませんがベテランの職人さんは削るときに出る屑ですら、綺麗な出方などこだわりを持っています。
それくらい仕上げに関してはより綺麗に!といった思いも強いです。
道具の専門的な部分も少し出ましたが、そちらに関してはまたの機会に。
それでは今日も一日がんばりましょう!!