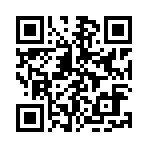2014年07月03日
今日の木地(尺貫法)
おはようございます。昨日は、ジャンルは違いますが木に携わるそれぞれのスペシャリストとお話しをさせて頂き、
とても刺激的な日になりました。
同じ材を扱うスペシャルリストのそれぞれの想い・こだわりが職種は違えど通ずるものでとても熱い時間でした。
さて、今日の木地です。今日は単位などを紹介したいと思います。
統一単位としては、廃止されていますが、まだまだ尺貫法が健在です。一般の方には、あまり縁のない単位だと思います。
【尺貫法(しゃくかんほう】
長さ・距離などをします"尺"に対し、質量などを示す"貫"です。
"尺"はM、CM、MMと同じように単位ごとに、【尺(しゃく)】、【寸(すん)】、【分(ぶ)】と言った単位があります。
1尺=10寸、1寸=10分といった換算されます。現在では1㎜が基準ですが、同じように1尺(303㎜)が基準で
換算すると誤差が生じやすいんですが、1寸(30.3㎜)、1分(3.03㎜)単位で扱います。
今でもベニヤ板などの規格は3尺×6尺、4尺×8尺というように尺による大きさで流通しています。
これはサブロクバン:幅3尺(910㎜)、長さ6尺(1820㎜)、
シハチバン:幅4尺(1230㎜)、長さ8尺(2430㎜)となっています。
規格が尺貫なのでおのずと、道具も尺、寸、分で呼び鑿(のみ)であれば○分鑿、○寸○分鑿と呼び、元々の決まっている彫り込み幅に合わせ鑿幅が設定されています。鉋(かんな)、鋸(のこぎり)も同様な呼び方でサイズがあります。
仕上の際は、○分面(面取り幅を指す)と言ったり、
材を呼ぶ時は、30㎜角を一寸(いっすん)材、45㎜角をいんご角と呼び、長さが10尺を超えたものは、長尺(ちょうじゃく)、長さがまちまちだと乱尺という表記をすることもあります。
原木材料の価格の基準なども、石(こく)と呼ぶ、10尺(3.03M)×1尺(0.303M)×1尺(0.303M)基準の設定からの
算定で取引されています。
尺とは関連はないのですが、数量の単位も丁、束と呼び一般的な本、バンドルのような意味合いで使用しています。
(束は材により束ねた数量が違うのでアバウトな呼称です)
こういったように現在でも職人さんの間では、旧来からの呼称の方がしっくりくる単位として使用されています。
この他、間取り基準での単位もありますが、それはまたの機会に。
僕自身は、もちろんメートルも使いますがメートルからの変更換算と言うよりも呼称は尺の方が自然と入ってきます。
習慣的なもので無意識ですね。
さて、今日はメンテナンスの日になりそうです。
今日も一日がんばりましょう!!
とても刺激的な日になりました。
同じ材を扱うスペシャルリストのそれぞれの想い・こだわりが職種は違えど通ずるものでとても熱い時間でした。
さて、今日の木地です。今日は単位などを紹介したいと思います。
統一単位としては、廃止されていますが、まだまだ尺貫法が健在です。一般の方には、あまり縁のない単位だと思います。
【尺貫法(しゃくかんほう】
長さ・距離などをします"尺"に対し、質量などを示す"貫"です。
"尺"はM、CM、MMと同じように単位ごとに、【尺(しゃく)】、【寸(すん)】、【分(ぶ)】と言った単位があります。
1尺=10寸、1寸=10分といった換算されます。現在では1㎜が基準ですが、同じように1尺(303㎜)が基準で
換算すると誤差が生じやすいんですが、1寸(30.3㎜)、1分(3.03㎜)単位で扱います。
今でもベニヤ板などの規格は3尺×6尺、4尺×8尺というように尺による大きさで流通しています。
これはサブロクバン:幅3尺(910㎜)、長さ6尺(1820㎜)、
シハチバン:幅4尺(1230㎜)、長さ8尺(2430㎜)となっています。
規格が尺貫なのでおのずと、道具も尺、寸、分で呼び鑿(のみ)であれば○分鑿、○寸○分鑿と呼び、元々の決まっている彫り込み幅に合わせ鑿幅が設定されています。鉋(かんな)、鋸(のこぎり)も同様な呼び方でサイズがあります。
仕上の際は、○分面(面取り幅を指す)と言ったり、
材を呼ぶ時は、30㎜角を一寸(いっすん)材、45㎜角をいんご角と呼び、長さが10尺を超えたものは、長尺(ちょうじゃく)、長さがまちまちだと乱尺という表記をすることもあります。
原木材料の価格の基準なども、石(こく)と呼ぶ、10尺(3.03M)×1尺(0.303M)×1尺(0.303M)基準の設定からの
算定で取引されています。
尺とは関連はないのですが、数量の単位も丁、束と呼び一般的な本、バンドルのような意味合いで使用しています。
(束は材により束ねた数量が違うのでアバウトな呼称です)
こういったように現在でも職人さんの間では、旧来からの呼称の方がしっくりくる単位として使用されています。
この他、間取り基準での単位もありますが、それはまたの機会に。
僕自身は、もちろんメートルも使いますがメートルからの変更換算と言うよりも呼称は尺の方が自然と入ってきます。
習慣的なもので無意識ですね。
さて、今日はメンテナンスの日になりそうです。
今日も一日がんばりましょう!!